「あなたの価値をAIが奪う!」オフィスワーカーが生き残るために必要な力とは?
そのうちいずれか1つでも当てはまるようであれば、それは赤信号が点灯している状態です。今すぐこの本を閉じて、ChatGPTを触り、その現在の実態を確かめてから、この先を読み進めていただきたいと思います。
AIを「使う」だけでは生き残れない
そして大切なのは、AIを活用すること、使いこなすことも当然重要なことではあるものの、それは決してゴールではない、ということをきちんと理解しておくことです。現代で「Google 検索ができる」というスキルが何の強みにもならないのと同様、AIをそれなりに使えることは、もはや前提となっていきます。
ゲームのルールは、すでにもっと大きく変わっていて、論点は「あなたがAIを使えるかどうか」ではなく、「AIがあなたの世界の前提をどこまで覆すか」というところにあるのです。あなたは、それに対して個人の力でどこまで抗うことができるのか。あなたは自分で自分の未来を切り開いていけるのか。それが強く問われています。
具体的なアクションとして求められるのは、AIを触り、AIの特性を知り尽くしたうえで、さらに「自分がAIに勝てる何か」を手に入れること。そしてそれを押し広げていき、「AIと戦わないためのゲームボード」を自分で用意できる力を持つことです。そうでなくては、今後のビジネスシーンで「できる人」の枠に入ることはできないでしょう。
もちろん、その「何か」は1つしかないわけではありません。しかし、その多くがある程度の才能や特別な経験を必要とするスキルだと思われます。そうした特筆すべき素養を持たない、平凡なオフィスワーカーが、今からでも会得できる「何か」こそ、「はみ出す力」なのです。
必要に応じてAIをフルに活用しつつも、要所で「自分だけのものの見方」に基づく「自分だけのまったく新しい提案・アイデア」を出す力。そして「自分だけの存在感」に基づく「自分だけの実行力」によって、組織を新たな市場・新たな競争に導く力。
そんな「正しくはみ出していく力」を養い、育んでいくことが、これからのビジネスパーソンには強く求められているのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

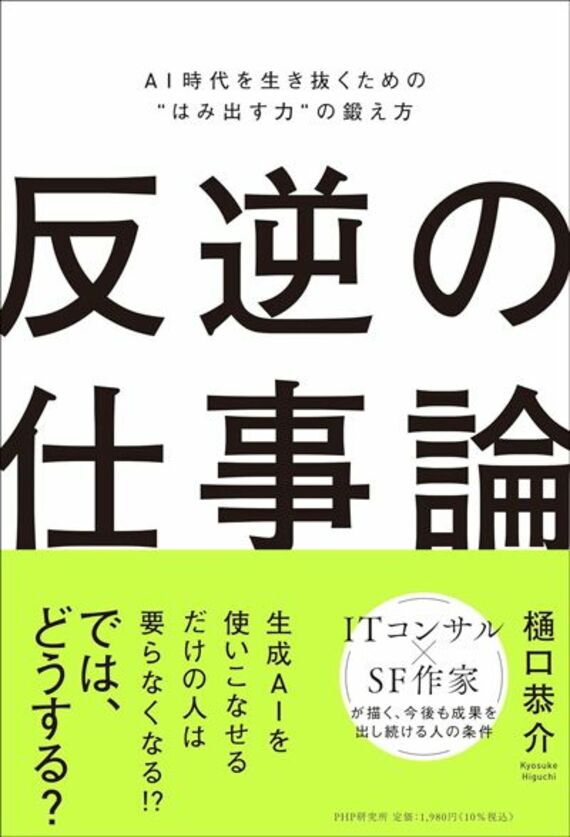
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら