長年培ってきた特別支援学級のノウハウが通用しない焦り
採用された教材は、ルビが振られていなかったり、回答時に問題が隠れてしまったりと、不具合も多かったそうだ。秋山さんは、「せめてアプリやソフトに長けた教員や支援員の配置を」と訴えるが、ほとんどの業界で人手不足が起きている今、簡単に実現できる話ではない。その結果、アナログに戻している部分もあると明かす。
「授業前にPCを触って興奮状態に陥ってしまうよりは、読書で気持ちを落ち着けてもらったほうが、スムーズに授業を始められます。また、紙のドリルのほうが、教壇からも進み具合やつまづいている箇所がわかり、すぐに対応することができます。プログラミング学習ソフトも、同級生と関わらず黙々と進めるタイプのものについては、学校に来ている意味がないのではないかと思ってしまいます。世界でも一部『アナログ回帰』が進んでいると聞きますが、それも理解できます」
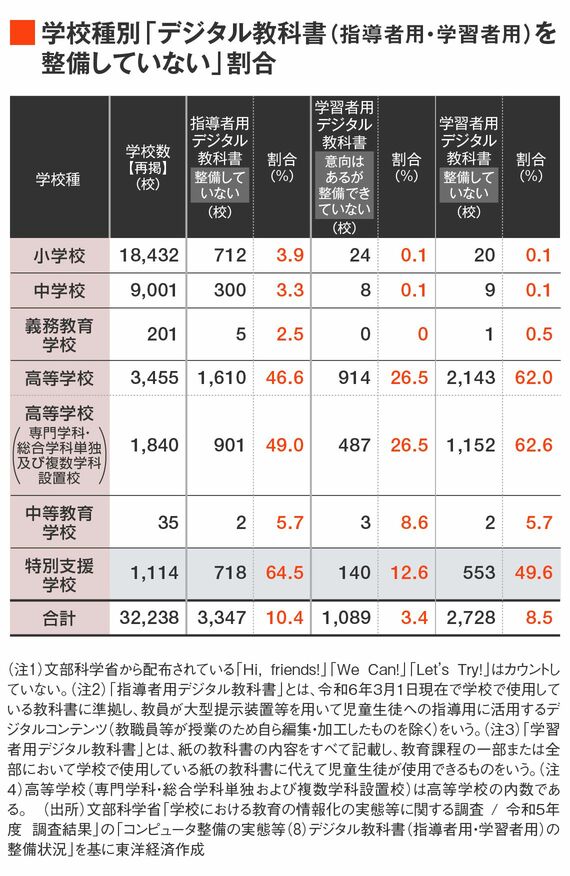
秋山さんの言うとおり、教育・IT先進国であったスウェーデンやフィンランドでさえ、学力低下や集中力低下を理由に、紙の教科書に戻す「脱デジタル化」を進める地域が出ている。ICT教育に課題を抱え、再検討を行う国があるのは事実だ。しかし他方で、社会全体ではAIの実装が進むなど、デジタルシフトが完全に見直されるとは到底考えにくい。今後は、アナログとデジタル、それぞれの良さをいかに生かすかが肝となるだろう。
「以前まで、授業前は机の上を鉛筆だけにして、手をひざの上に置いてもらい、気分高揚や注意散漫な状態を抑えてから授業を始めていました。特別支援学級で長年培ってきたノウハウが、一瞬にして使い物にならなくなってしまった感覚です。ICT教育を進めるのであれば、優秀な先進事例を集めて眺めるのでなく、いろいろな失敗事例を共有しあって新たなノウハウを生み出していく体制があるとよいのではと思います」
秋山さんが指摘したように、学校や自治体を明かして失敗事例を共有する場合、児童個人が特定されてしまうリスクもある。しかし、失敗と対策の情報は、足元の課題を解決するために何より有用なはずだ。一部を抽象化やマスキングすることで、貴重な教育資産として蓄積できないのか。このままでは、ICT教育が尻すぼみになる学校と、ICT活用が進む学校との格差が広がるばかりである。ICT教育の適切な普及のために、価値ある提言ではないだろうか。
(文:高橋秀和、注記のない写真:Graphs / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































