利用者増加中のがんリスク検査はエビデンスに基づくのか。

サリバテックの検査センター(山形県鶴岡市、撮影:岩澤倫彦)
人の命を左右することもある医療情報。SNS上では私たちの不安につけこんだ、根拠に乏しい情報があふれている。本特集のタイトルは「不安につけこむ『医療情報』の罠」。何を信じ、何を疑えばいいのか。
血液、尿、唾液から、複数のがんに罹患(りかん)している可能性を判定できるという「がんリスク検査」が次々と登場している。
がんから命を守るためには早期発見・早期治療が重要なのは言うまでもない。そのためにがん検診があるわけだが、多忙な現代人は、ついおろそかにしがちだ。
「がんリスク検査」は血液などを採取して検査会社に送るだけ。この手軽さが好評で利用者が増え、最近はふるさと納税の返礼品に採用されるようになった。
医師からは懸念の声
一方、がん医療に携わる医師からは、正確にがんを発見できるか疑わしいという懸念の声も上がっている。実態はどうなのか──。
トピックボードAD
有料会員限定記事

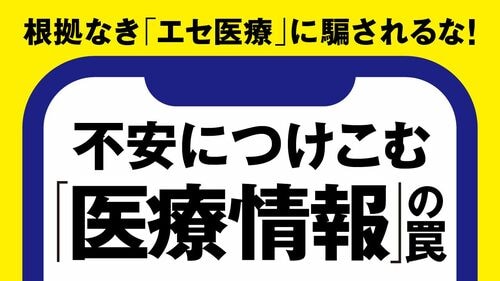































無料会員登録はこちら
ログインはこちら