
公立学校教員に残業代(時間外勤務手当)を支給しない、教職員給与特別措置法(以下、給特法)を維持する方針が、5月13日の文科省の中央教育審議会(以下、中教審)で決まった。
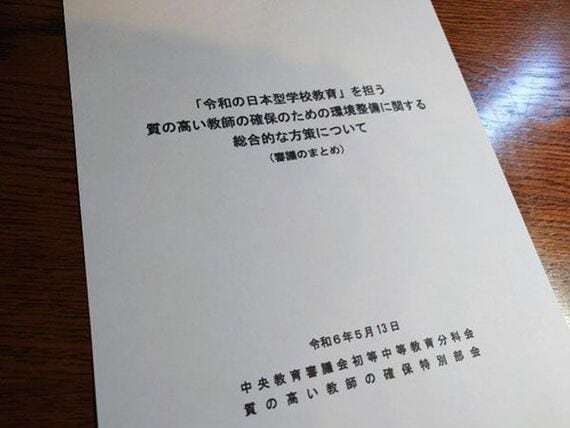
報道されているように、このことに対して、現役教員や研究者、弁護士などからの批判は強い。「仕事が多いなら残業代を出すのは当たり前だ」との考えは共感できるが、残業代を出す制度が本当に望ましいベストな選択と言えるかどうかは、少し立ち止まって考える必要がある。
ここでは、中教審での検討結果や問題を含めて解説する。なお、私も中教審の臨時委員として今回の審議に関わってきたが、代表する立場ではないし、個人の見解を述べる。
給特法の問題はどこにあるか
まず、現状はどうなっているのか。給特法という特別法が公立学校教員(以下、教員)には適用されており、残業代は出ていない。ただし、月給の4%が教職調整額として加算されている。教員にも労働基準法は適用されているのだが、給特法において時間外勤務手当などの一部を適用除外としているのだ。
教員志望者の減少や教員不足・欠員など、人手不足が深刻化する中で「残業代を支給しない給特法を変えるべきだ」という意見は多方面から寄せられている。給特法廃止論とここでは呼ぶことにするが、その主な理由は3点ある。
1. 時間外の業務の多くを「労働」として認めて、対価を払うのは当然である。また、そうした時間外の業務を使用者(校長、教育委員会)の管理監督責任のもとに置く必要がある。
2. 時間外勤務手当(割増賃金)というサンクション(制裁)を使用者に課すことで、使用者のコスト意識を高めて、業務の精選、見直しなどを加速させる。
3. 36協定を結ぶことで、労使間のコミュニケーションを通じて、業務の拡大に歯止めをかける。
これらは逆に言えば、現行制度である給特法の問題なのだが、ある程度、説得力があるように思う。とりわけ、大学生らにとっては、働いたのに残業代も出ないようなアルバイトや仕事はほとんどないし、「給特法はおかしい」と感じている人も多いことだろう。
だが、どのような制度もいいことづくめではなく、廃止にも難点や懸念されることがある。功罪を冷静に考えて、なるべくプラスが大きく、マイナスが小さくなるような制度とするべきだ。給特法廃止論の論拠に対応させながら、説明しよう。
【論点①】時間外業務かどうかの線引きができるか
1つ目の時間外業務に対価を払うことに関連して、教員が行っている時間外の活動のうち、どこまでが業務(公務)で、どこまでが業務外(自己研鑽やプライベートな活動)なのかを、明確に線引きできるかどうか、という問題がある。
確かに、時間外に行っている部活動指導、児童生徒や保護者との相談、テストの準備や採点、事務作業などは学校の仕事、業務(公務)であり、給特法を廃止した場合、残業代の支給対象となろう。一方で、やっかいなのは授業準備や教材研究、授業研究である。
もちろん、教員の本務は授業のため、その準備や研究は大事だ。だが、例えば、英語科の教員が学校で洋画を鑑賞しているとしよう(現実にはそんなゆとりのある学校現場は少ないが)。授業で使う場合は業務の性格が強いものの、授業で使うかどうかはわからないが勉強にもなるし観ているという場合であれば、自己研鑽や趣味、プライベートという気もしてくる。
部活動指導についても、生徒の活動を見守ったり、助言をしたりしている時間は業務性が強いし、顧問の先生は監督者としての責任を問われうる。一方、指導者ラインセンス資格を取得するための勉強をしたり、大会の運営事務を行ったりしている時間は、学校の業務と言えるのかどうか議論の余地がある。
ただし、業務かどうか峻別が難しいものがあるからといって、給特法を維持すべきと結論付けるのは、ロジックの弱い、かなり雑な主張だと思う。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら