実践の経営学を探究する井上達彦教授が、ディープテックが世界に羽ばたくための要素を探る。スタートアップが持つ技術の芽をいかに育むか。

井上:日本のベンチャーキャピタル(VC)は世界標準から離れ、遅れていると伺います。
瀧口:日本のスタートアップの業界というのは、ある意味でガラパゴス的なんですね。これは悪い意味ではなくて、日本的なんです。シリコンバレーのベンチャーの動きと日本の動きは基本的に違いますから。
どちらがよいかという問題ではなく、根本的にゲームが違うんです。だから、私も日本でゲームをやるときは、日本型のゲームとして参加しています。でもアメリカで投資するときはグローバルなゲームだと理解してやります。
「その場で決める」アメリカ、裏付け求める日本
井上:何が違うのでしょうか。

瀧口:アメリカだと役割分担が明確なんです。アーリー、ミドル、レイターそれぞれのステージを得意とする投資家がいて、全員がリスペクトし合っている。役割分担ができているので判断も早いです。
いい案件があったら、その場で感触を伝えます。話を聞いた瞬間に「金額の大小は別にして、とにかく出すから」と伝え、その瞬間に握ってしまうわけですね。
一方、日本の場合は役割分担が明確ではなく、組織の意思決定ですから裏付けや根拠が求められます。主に、ミドルステージ以降でゲームが進められるので判断材料も徐々にそろってきます。意思決定の場面でも「社内の投資委員会にはかるので3カ月待ってください」というのが少なくありません。
日本で求められるのは、日本市場に最適化された国内ゲームです。そのゲームでしっかり利益を上げていくことを考えているわけですから、セコイア・キャピタル(アメリカの大手VC)が求めるような巨大ビジネスを目指していません。



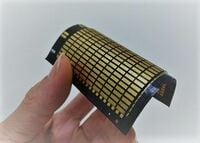





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら