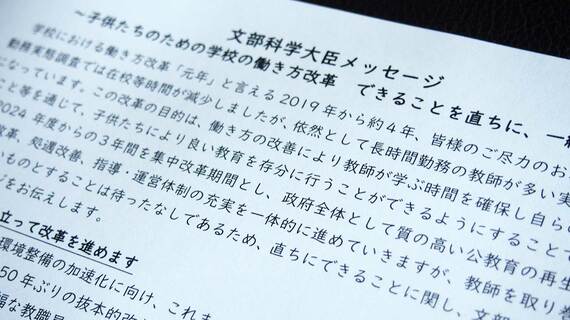
今年8月28日に文部科学相の諮問機関、中央教育審議会(以下、中教審)の特別部会は、学校の働き方改革などについて、緊急提言を出した。これを受けて、文部科学省は8月29日に大臣メッセージを発表するとともに、9月8日に取り組みの徹底を求める通知を全国の教育委員会等に発出している。
中教審が主張する取り組みはどんな内容なのか。そもそも、なぜそうした呼びかけをしているのか。はたして、意味のある取り組みなのだろうか。
私自身、中教審のこの部会の委員の一人として関わっているし、ここ数年、学校の働き方改革について数百件の講演や研修を担当してきた当事者でもある。以下では、私なりの視点からなるべくわかりやすく解説したい。とはいえ、妹尾は中教審を代表する立場ではまったくないし、文科省の役人でもないので、個人的な見立て、見解になることはご了承いただきたい。
大臣が直ちに取り組む
まず、文科大臣が出したメッセージを下記に掲載した(内閣改造で大臣は代わったが、基本的に内容は引き継がれるはずだ)。
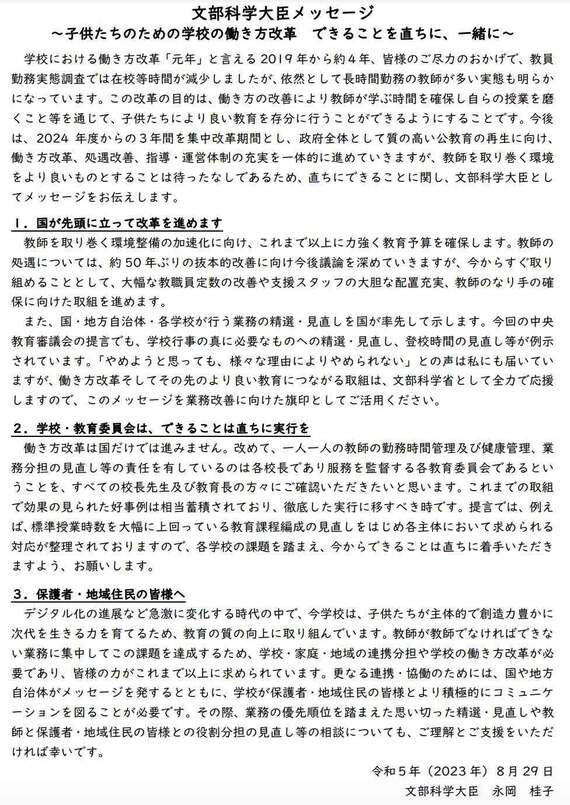
「国が先頭に立って改革を進めます」「これまで以上に力強く教育予算を確保します」「国・地方自治体・各学校が行う業務の精選・見直しを国が率先して示します」など、かなり威勢のよい言葉が並んでいる。
「この言葉どおりになればいいな」と思うのと同時に、「だったら、なぜこの4~5年の間はできなかったのか」とも感じる。これまでの取り組みを真摯に反省することは重要だと思うが、とはいえ、文科省が学校の働き方改革について優先度を上げて取り組むという姿勢を見せていることは、いいことだと思う。
学校の先生たちからたまに聞くのは、一教職員が何か改善したくても、校長や教育委員会が消極的で進まない、という声だ。そういうケースには、この文科大臣メッセージを見せてみよう(それでも、できない言い訳ばかりが得意な人もいるが……)。
なぜ、緊急の提言、メッセージなのか
さて、どうしてこのようなメッセージ、また緊急提言という形になっているのだろうか。
さまざまな背景があるが、一つ大きいのは、深刻化する教員不足、講師不足である。教員志望をやめた大学生等も少なくないし、教員採用試験でも中学校・高等学校教員については、新卒の受験者数は減少傾向である(全国計)。また、どの校種でも、非正規雇用で不安定な職である講師を務めてでも、正規の教員を目指そうという人が少なくなってきている可能性が高い。
こうした教員志望者、講師志望者の減少の背景・要因もさまざまだが、大学生等への調査では、やはり、学校の過重労働、過重負担が問題視されているのは明らかだ。しかも、忙しすぎて、同僚などへ支援・ケアする余裕のない職場では、休職や離職も増えていく。残された人はさらに多忙になる。悪循環である。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表
徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中
(写真は本人提供)































無料会員登録はこちら
ログインはこちら