「人が怖い」社交不安症は心の病気、思春期に発症傾向あり必要な教室対応は? 人前での赤面に手の震え、過剰な不安に苦しむ
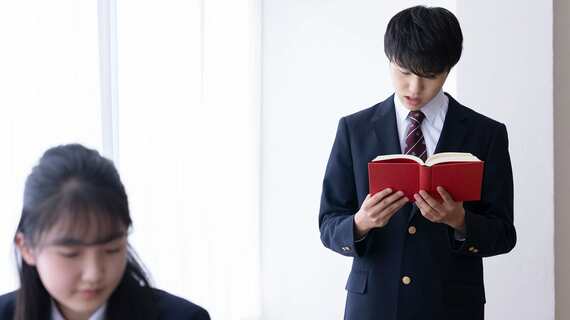
人前での「赤面」「手の震え」、社交不安症はれっきとした病気
社交不安症は、突然の動悸や呼吸困難、激しい不安に襲われる「パニック症」、愛着を持つ場所や人物から離れることに過剰な恐怖を抱く「分離不安症」などの「不安症群」にカテゴライズされる強い不安の病気だ。かつては対人恐怖症や社会不安障害とも呼ばれていたが、現在は社交不安症という診断名に統一されている。
社交不安症の問題は、「人前で失敗したくない」「相手に自分の振る舞いをバカにされるのではないか」という考えが強すぎる点だ。強い不安が起こす身体反応として、人の視線を感じると「体が震える、固くなる」「顔が赤くなる」「汗だくになる」、人と話そうとすると「頭がまっしろになる」「声が震える」などがあり、本人はその身体反応を隠そうとする。不安な自分を見せまいと、マスクをしたり、自分から話をしないような行動をとるという。
こう聞くと、「病気ではなくシャイなだけでは?」と疑問に思う人もいるかもしれない。しかし社交不安症は、WHOや米精神医学会などが公表している基準で診断されるれっきとした病気だ。清水氏はこう説明する。

千葉大学大学院医学研究院教授
千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター センター長
千葉大学子どものこころの発達教育研究センター センター長
認知行動療法のスペシャリストとして、不安症(社交不安症、パニック症など)、強迫症、うつ病、慢性疼痛、不眠症などの治療に、複数のセラピストとともに当たる。著書に、『自分で治す「社交不安症」』(法研)、『あれこれ気にしすぎて疲れてしまう人へ 精神科医30年のドクターが教える傷ついた心の完全リセット術』(徳間書店)、『ナイーブさんを思考のクセから救う本』(ワニブックス)など
(写真は本人提供)
「人前での発表や面接などで不安を感じることは、誰でも経験があると思います。しかし、社交不安症は、毎日毎日の日常会話にも強い恐怖を感じてしまい、かつ状況に慣れることができません。子どもであれば不登校、大人なら職業選択の幅を狭めるなど、社会生活に支障を来します」
例えば、毎日教室に入るのがつらくて仕方ない、人と話す給食の時間が来るのが怖いなど、いたって日常的な場面でストレスを感じるが、中核にあるのは他人から見られているのが怖い「視線恐怖」だと清水氏は説明する。































