先に家の中へ足を踏み入れた教頭が声を上げた。「もうダメだ……」。K先生は自宅で首を吊り、亡くなっていた。若井さんは葬儀にも参列したが、ずっと違和感を抱えていたという。
「あまりにも情報がないんです。もちろん口にするのがはばかられる出来事ではありましたが、それにしてもK先生の死について、誰も何も言わないし、聞こうともしない。異様な雰囲気だと感じました」
同年、うつ病での休職者が現れた
そんな中、もう一つの事件が起こる。2学期が始まった頃、A先生が学校に来なくなった。顧問をしていた部活動の大会も控える中、パッタリ出勤が途絶え、そのまま休職してしまったのだ。
「彼がうつ病だったことは、後に本人から教えてもらいました。事情を尋ねると、『K先生の死はA先生のせいだ』と複数の教員から繰り返し責められていたと告白されたんです」
実は、A先生はクラス替えの際、「自身の担当教科に関心がある生徒たちを担任したい」と申告していた。そのため、A先生の担当教科が相対的に苦手な生徒は、ほかのクラスに集中することに。この“シワ寄せ”がK先生の元に波及し、K先生が心を病んでしまったのだというのだ。クラス編成の腹いせにつくられた、言いがかりともいうべきシナリオだった。
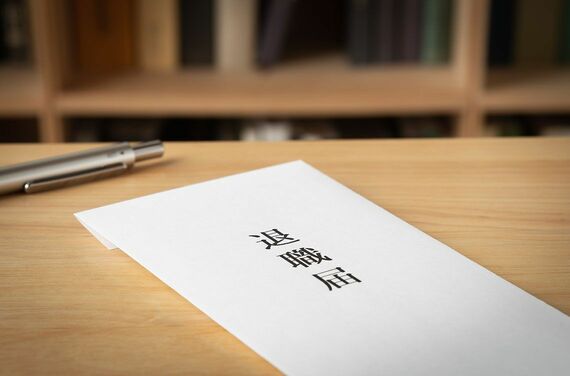
(写真: CORA / PIXTA)
A先生は休養を経て一時は復帰したものの、結局うつ病が再発して退職。若井さんとは年賀状のやり取りこそあるものの、結局今日まで顔を合わせられずにいるという。
職員室という狭い空間の中で、何が起こっていたのか。なぜ自分は気がつかなかったのか。若井さんは今でも考え続けている。
それでも校長は、定年まで「無事」に勤続
今、若井さんが最も憤りを感じているのが、発端ともいうべき校長の処遇だ。
「K先生を追い込んだのは、初めに彼を叱責した校長です。もし同じことが民間企業で起こっていたらどうでしょう。ちゃんとした会社なら少なくとも、事実関係の調査やしかるべき処置がなされるのではないでしょうか。ところがこの校長はその後、定年まで勤め上げて、“無事”退職していきました」
人を追い詰めたことへの意識があまりにも軽い、と若井さんは声を詰まらせる。また、職員室の雰囲気も決してよいものではなかったという。若井さんは「学校によると思う」と前置きしながらも、教職員が積極的に関わり合うことはなく、K先生が亡くなった時も、教員たちの受け止め方が非常にドライで、冷たいとさえ感じたと語った。
「自分の中でK先生のことが消化しきれず、ほかの先生に相談したこともあります。でも、『その話はもうやめよう』といなされました」
若井さんは、たまらずK先生の父親の元へ足を運んだ。経緯を聞いたK先生の父親も、一時は発端であり責任者でもある校長を訴えようと思ったそうだが、土下座で謝罪をされ、結局裁判には至らず。校長は最後まで“おとがめなし”だった。
若井さんは教育委員会にも事実関係を問う手紙を送ったが、「該当職員の権利を損なうおそれがあり、回答はできない」と、はっきりした情報は何も得られなかった。






























