「忙しいのは教員だけではない」が大前提、学校の働き方改革進める4つのヒント 文部科学省主催フォーラムで識者が語ったこと
まずは互いに共感し、共に知恵を出そうという空気をつくることが大切だと語った。
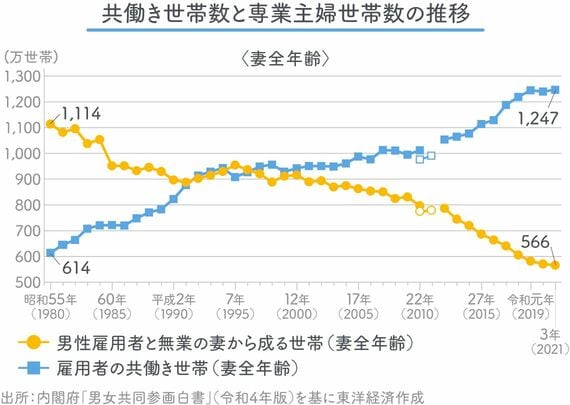
もう一つ同氏が強調したのは、「小さな成功」を積み重ねることの有効性だ。デジタル化を推進する際、「そのよさを生かそうと頑張りすぎる学校」では、新たな負担が増えやすいという。環境整備のためだとしても、度重なるアンケートを実施したり強制的な雰囲気を醸し出したりすると、保護者はデジタル化に対してマイナスイメージを抱いてしまう。まずは難なく納得してもらえる程度の小さなことを実践してみて、確実な成功体験を積むこと。最初から大風呂敷を広げるのではなく、コツコツ進めることが近道のようだ。
奈幡氏も、「守谷のニューノーマル」として進めたデジタル化の一例を示した。
「守谷市では絵画や書道の作品を撮影してクラウド管理することで、教員が作品掲示に割く時間を減らすことができました。1校が単独でやるのではなく、市全体が同じ歩調で取り組めたことも大きかったと思います。デジタル化は保護者こそが望んでいたこと。皆の生活がスマートになることは、教員の授業研究を充実させ、働き方改革だけでなく学び方改革にもつながります」
コントロールを手放して、他者と協働しながら効率化を図る
もう一人、事例紹介で登壇した上部充敬氏も、新保氏と同様のことを語っていた。上部氏は横浜市立日枝小学校で事務職員として働いており、この日は「教員以外の視点」から働き方改革について述べた。
「私は学校でグループウェアを導入しようと言って、大反発に遭ったことがあります。そこでまず簡単なチャットソフトを入れたら『これはいい、もっと機能があるものが欲しい』という意見が出て、結局グループウェアを入れることになりました」と笑い、「小さく実行して、成功のプロトタイプをつくることで早く効果を体感する」ことが重要だと続けた。
上部氏はほかにも、自身の経験から業務改善のポイントを挙げた。とくに強調したのは「一人で丸抱えしないこと」。例えば事務職員が行う備品の補充は、本来は教員の授業や子どもの学習を支えるためのものだ。だが上部氏はいつしか自分が完璧に管理することが目的になってしまい、ほかの担当者に触らせない状況をつくってしまっていたという。
「その結果、自分が休むと在庫補充が滞り、子どもや先生が困ることになりました。限られた時間で効率を上げるには、コントロールを手放しながら、しっかりとリーダーシップを取ることが大切です」
上部氏は「今はまだ、学校は従来の戦力で戦おうとしていると思います。でも学校にもいろいろな人がいて、戦力図は変わってきている」と語る。同氏の学校では地域の障害者施設と協働し、エアコンのフィルター掃除や教室のワックスがけといった、これまで教員が担当してきたが教員以外でもできることを委託しているそうだ。保護者や地域の理解を得る方法としても、「担任だけではなく学校にはいろいろな教職員がいるし、事務職員もいる。担任以外の人に話しかけて解決できることもあると知ってほしい」と続けた。
本フォーラムの談話やパネルディスカッションを通じて実感させられたのは、「忙しいのは教員だけではない」ということだ。保護者も地域住民も事務職員も、そしてもちろん教員も時間に追われている現代。集まった有識者たちが呼びかけたのは、その大前提を認識したうえで、共感し合い支え合うことの必要性だった。人口減少や教員不足が叫ばれる今日、学校に関わるすべての人が「働き方改革」のための重要な戦力であり、当事者であるはずだ。
(文:鈴木絢子、写真:foly / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























