「忙しいのは教員だけではない」が大前提、学校の働き方改革進める4つのヒント 文部科学省主催フォーラムで識者が語ったこと
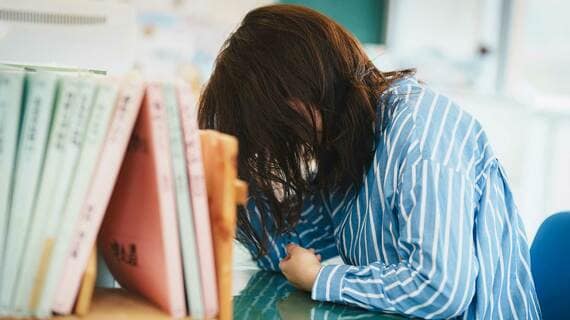
「働き方改革チェックシート」で「伸びしろ」を探そう
文部科学省では2021年3月に「全国の学校における働き方改革事例集」を公開した。これはどんな取り組みによってどんなふうに業務改善が実現されたかという情報をまとめたもので、当該ホームページから確認することができる。文科省は各校でこうしたアイデアを取り入れて、働き方改革に役立ててほしいと考えている。また、オンラインで開催される「学校における働き方改革フォーラム」はこの事例集を広める狙いもあり、教員や教育委員会のみならず、保護者も含めた学校関係者を対象に実施される。
今年3月に行われた同フォーラムでは、さらに一歩踏み込んで、Excelで公開されている「働き方改革チェックシート」の活用法も示された。このシートでは業務内容が14の項目に分類されており、細かくチェックしていくことで、自校の具体的な改善点を探ることができる。説明したのは茨城県の守谷市教育委員会参事である奈幡正氏だ。
「このチェックシートのよさは『実用的』であることで、シートのファイルから事例集に直接アクセスすることもできます。事例集はすでに3回の改訂を経ていますが、忙しくて開く時間のなかった先生も多いでしょう。そうした方々にもぜひ使っていただければ」と、忙しい教員に寄り添いながら話した。「先生の幸せ研究所」代表の澤田真由美氏も「これはチェックすることで一喜一憂するためのものではなく、自校について深く考えていくための素材ですね。まだまだだなと感じる部分はむしろ伸びしろだと捉えて」と、新たなツールの活用を呼びかけた。
デジタル化推進のために「共感」と「小さな成功」を
事例の説明では、現場を知る2人の有識者が登壇した。1人目は札幌市内の小学校で校長を歴任した新保元康氏。現在はほっかいどう学推進フォーラムの理事長を務めている。新保氏が語ったのは「学校・保護者等間の連絡手段のデジタル化」についてだ。
同氏がデジタル化の重要性を痛感したのは2011年3月11日のことだった。言うまでもなく、東日本大震災が起こった日のことである。
「当時勤めていた小学校では、すでに緊急連絡の手段としてメールを活用していたので、すぐに保護者に安全確認の連絡をすることができました。とても安心していただけたことを覚えています」と語り、緊急時だけでなく、なかなか進まない「日常の連絡のデジタル化」についてもその重要性を説いた。新保氏はデジタル化の一環としてプリントの数も減らしたが、保護者はそれらの配布物を「紙爆弾」と呼んでいたという。
印象的だったのは、「どうすれば保護者の理解を得ることができるか」という点を説明した際の言葉だ。新保氏は共働き世帯数の推移のグラフを示しながら語った。
「2000年ごろから専業主婦が激減し、多くの家庭が共働きになっています。忙しいのは高齢者も例外でなく、横断歩道の見守りをしてくださっていた地域のお年寄りが『介護をしなければならないので、見守りボランティアを降りたい』と願い出てきたこともありました。先生だけでなく、今は保護者もみんな多忙の時代。ある保護者の集まりで、私が『お母さんも忙しいよね』と言ったところ、『わかってくれた』と感じたのか、相手の顔がぱっと変わりました」






























