小学校より負担減でもネガティブな印象が付きまとう「中学校PTA」のリアル 生徒会とコラボ、キャリア教育など活動に幅
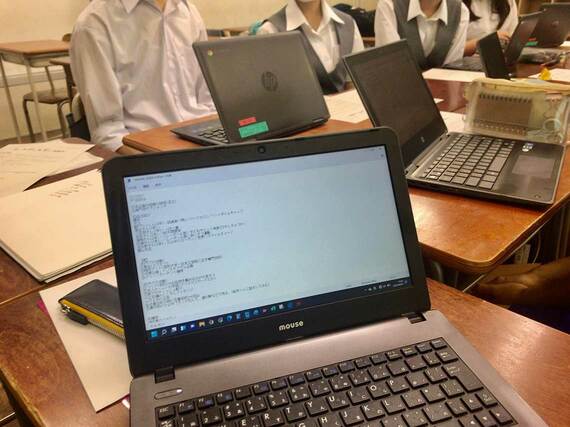
(写真:櫻井氏提供)
「階段アートや黒板アートについては、八王子市内に美術系の大学や専門学校がたくさんあるので、描いてくれる学生を見つけて生徒会につなげたり、農作物の販売についても、地元で農業系の仕事をしている知り合いを巻き込んだりすることができます。PTAが中心ではなく、生徒会と一緒に考え、彼らの思いやプランを後押しする役割に徹しながら企画の実現に向けて進めていくことで、新しい世界が開けるのではないかと思います。
生徒会担当の先生も、座談会でいろいろ話しているうちに、『制服のルールを簡素化したい』というお考えをお持ちであることがわかりました。現場の先生は、校長先生や保護者代表、地域住民などからなる学校運営協議会の活動内容について詳しく知らないことも多いので、PTAからも情報を提供しながら現場の先生の意見も取り入れていきたいですね」
「委員会制」「一人一役制」を廃止
子どもが中学生になると、登下校が自由になることに加え、部活動など親よりも友達との交流を優先して時間を過ごすようになり、小学校の時のような安全パトロールやPTA主催の親子イベントの開催などの必要性も減る。
学校、子ども、保護者にとって必要な活動を精査し、適正化、効率化を図りやすいのも、中学校のPTAの特徴といえるのではないだろうか。
ひよどり山中学校では、2021年度より、これまで慣例的に続いてきた「委員会制」「一人一役制」を廃止。「新入生の保護者が、入学式終了後体育館に残され、委員決めをする」という、“前時代的な恒例行事”をなくした。

(写真:櫻井氏提供)
「委員会制を廃止したため、PTA活動についての決め事は、本部役員13名(女性8名、男性5名)で行っています。新入生の保護者に向けての役員募集は、入学前の2月ごろに学校が開催する新入生保護者説明会の時に資料を配布しGoogleフォームから立候補者を募りました。『できる人が、できる時に、できることを』を実現することができる体制と運営について理解していただき、4名の新入生保護者から手が上がりました。
現在は、運動会の際の受け付けや写真撮影、校内美化作業などでお手伝いが必要な際に、その都度Googleフォームからサポーターを募集し、スムーズに運営しています。本部役員は、形式上、会長・副会長・書記・会計の役職は存在していますが、LINE WORKSを導入し全員で協力しながら運営しており、中学校や子どもたちの学校生活に対する興味が少しでもあれば、“誰でもできる本部役員”であるといえます。多くの保護者がPTA活動を前向きに楽しめるよう、発信を続けていきたいと思います」(櫻井氏)
NPO法人のキャリア教育プログラムを導入
NPO法人や地域とコラボし独自の取り組みを行う中学校PTAもある。東京都豊島区立明豊中学校(家庭数:394、PTA加入率:100 %)だ。

東京都豊島区明豊中学校で、21年度からPTA会長を務める。これまでの「一人一役制」を廃止し、できる人ができることを行う方式で委員選出を行った。高校受験をテーマに保護者座談会も開催。3人の子どもの母親
(写真:森田氏提供)
同校で2021年度からPTA会長を務める森田絹枝氏は、「認定NPO法人キーパーソン21」で活動する知人を通し、同法人が展開するキャリア教育プログラム「わくわくエンジン®」の存在を知った。
「わくわくエンジン®」とは、先生でも保護者でもない社会人との出会いの中で、子どもたちが将来の仕事や生き方について考え、自分が本当に大切にしたいことに気づき、主体的に人生を選択して動き出す力を育むオリジナルの教育プログラムだ。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら