小学校より負担減でもネガティブな印象が付きまとう「中学校PTA」のリアル 生徒会とコラボ、キャリア教育など活動に幅
「職場体験」中止を受け「キャリアフェスティバル」を開催
中学校でのキャリア教育といえば、生徒が地域で働く人の職場に出向いて実際の仕事や技術に触れる「職場(職業)体験」がよく知られているが、近年はコロナ禍で中止・縮小を余儀なくされている学校も多い。
逗子中学校もそんな学校の1つだったが、大本氏の知り合いが住む長野県の公立中学校が、地域でさまざまな職業に就いている大人を学校に呼び、生徒と交流する「キャリアフェスティバル」を行っていることを知った。
「『コロナ禍で職場体験ができない場合は、このような形なら開催できるかもしれませんね。もし開催することになったら、PTAも全面的にお手伝いしますのでおっしゃってください』と学校に提案したところ、『総合学習の一環としてキャリアフェスティバルを実施することにしました。可能な範囲でご協力お願いできますか?』と、お返事をいただきました」
学校主導で企画・運営を行い、PTAは職業の選択とその職業に就いている地域の大人へ講師として来てもらうための声かけ、講師へのアンケート作成、当日の受け付けなどをサポートした。

(写真:大本氏提供)
キャリアフェスティバル当日は、市議会議員や医師をはじめ約30人の地域の大人が学校に集合。会場である体育館と各教室にブースを設け、4名程度の生徒のグループが1回につき40分ずつ、計3つのブースを選んで話を聞く方式で行われたという。
「子どもたちは、自作の名刺を使った名刺交換からスタート。最初は緊張していた様子でしたが、時間が経つにつれてリラックスし、気になる職業に就いている大人の方の生の声に刺激を受けている様子でした。講師の方からは、生徒から質問を受けて、自分の仕事やキャリアを見直すきっかけにもなったとおっしゃっていただきました。PTAからの提案を受け入れチャレンジしてくださった学校に、とても感謝しています。
中学生時代は多感な時期だからこそ、親だけ、学校だけで子どもたちのケアに取り組むよりは、保護者と学校がお互いに情報交換をしながら関わっていくことが大切だと感じています。保護者と学校が恒常的に本音で対話ができる関係をつくることに、中学校のPTAの存在意義を感じています」
生徒会とPTAのコラボ「SPTA」を発足
「中学校は、小学校とは異なり子どもたちに関わる活動が少なくなる部分はありますが、中学校なりの関わり方を、小学校とは違う視点で考えることが大切だと思います」と語るのは、2021年度より東京都八王子市立ひよどり山中学校(家庭数:259、PTA加入率:98.8%)でPTA会長を務める櫻井励造氏だ。
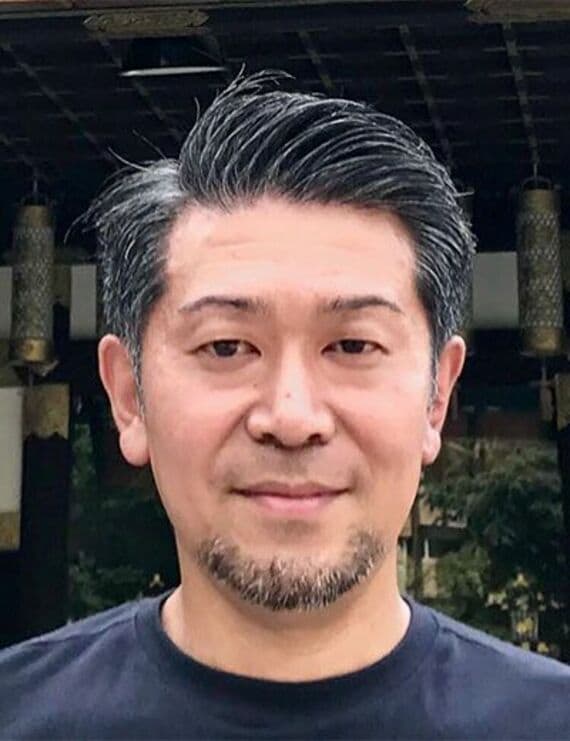
東京都八王子市立ひよどり山中学校で、20年度PTA副会長を経て21年度からPTA会長。おやじの会による職業トークの会「ジョブトーク」の実施、学校と協働し制服リサイクル販売などにも取り組む。八王子市立小学校PTA連合会の顧問も務める。3人の子どもの父親
(写真:櫻井氏提供)
櫻井氏は、かねてPTA本部役員として取り組みたいことの1つに「生徒会との意見交換会」を掲げていた。
「中学校の生徒会は、SDGs関連など自分たちでさまざまな活動をつくり出しています。生徒会とPTAとの共同イベントを開催したり、校則や高校受験などさまざまな観点から、生徒と保護者の垣根を越えて一緒に活動できたりするとよいのではないかと考えていました」という。
学校に提案したところ、「ぜひお願いします」と即答。「PTA」に、生徒会の頭文字である「S」を加えて「SPTA」と銘打ち、22年9月に第1回の座談会を開催した。
「会議のメンバーは、生徒会メンバー7名、PTA役員2名、生徒会担当の先生1名の、計9名。事前にSPTAの目的や座談会で話し合う内容を生徒会メンバーに伝えておいたのですが、非常に前向きに捉え、やりたいことを考えてきてくれました」と、櫻井氏。
「卒業式の日に、卒業生へのお祝いの気持ちを込めて階段アートや黒板アートをやってみたい」「学校を会場にフリーマーケットを開催したい」「校庭の畑で取れる農作物をブランド化して、道の駅などで売りたい」「グリーンカーテンや古着回収に取り組んでみたい」など、生徒会からさまざまな企画案が出たという。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら