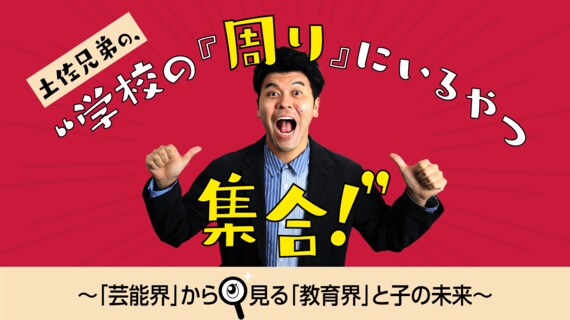卓也:絶対に見ないほうがいいやつですよ(笑)。
蓑手:僕が主張した、「学びは本来楽しいもの、もっと自由に楽しみながら力をつけることが大事」という考えには非常に多くの批判がありました。「何を言ってるんだ、苦行をしてこそ勉強だろ」とか、「歯を食いしばる力がないから最近の若者は駄目なんだ」というコメントを目の当たりにして、「そうか、世論は圧倒的にこっちか」と改めて実感しましたね。とくに強いのは保護者の声です。個々の学校はもちろん、文科省や教育委員会も、保護者に「NO」と言われれば動けないのが現実です。
卓也:保護者からすれば、「よりによってわが子の代で、なに試行錯誤してくれちゃってんの」という気持ちですよね。大事なわが子が、受験や就職への影響を含め、前例も確証もない改革に巻き込まれるくらいなら、今までどおりの手堅い教育をしてほしいと。
蓑手:われわれ世代にはどうしても、「そもそも仕事は我慢するもの。やりたい仕事ができなくても、そこまで幸せとはいえなくても、お給料をもらえるなら大したことない」という人生観があります。夢や憧れに執着せず、それなりの大学を出てそれなりの企業に入社すれば安泰なのだから、子どもに余計なことを吹き込まないでくれということでしょうね。
卓也:うわ、むっず………!!! 「今までの教育」を受けた結果、大人たちもそれなりに安定した生活ができているからこそ、抜け出せないわけだ。

蓑手:日本の学校教育に順応してうまくレールに乗れた人には自己肯定感がありますし、自分の経験を正当化したい気持ちも相まって、先の批判コメントのように「そんな貧弱じゃ駄目だ」と言うんです。一方で、ヒロック初等部のようなオルタナティブスクールに集まる人の多くは、さまざまな事情で日本の画一的な教育に疑問を抱いているんですよね。例えば、学生時代に海外の学校に通っていたり、不登校だったり……。「日本の学校っておかしくない?」と思っていた彼らの周りに、ようやく最近、モンテッソーリ教育など海外の情報を耳にした感度の高い親御さんたちが加わりはじめたところです。
卓也:僕なんかは、学校には前例にとらわれずに、子どもたち一人ひとりの可能性や多様性を見いだしてほしいと期待しちゃいますが、こういう親は少数派なんですか?
蓑手:お子さんが小さいうちは、親も「自由に育てたい」と考えているはずなんですが、いざわが子の受験が近づくと、「1つでも偏差値を上げてほしい」「少しでもよい大学に入ってほしい」という気持ちがにじみ出てくるんですよね……。
卓也:すべての親が「教育改革は構わないけど、うちの子だけは受験に成功させたい」と思っているから、一向に進まない。日本の社会構造が変わらないと、教育現場も変わりづらいですね。
蓑手:希望的な話をするなら、本当に少しずつですが社会構造も変わってきています。例えば、学歴社会の崩壊。企業の採用活動はあくまで能力を重視していますし、必ずしも学歴と能力が比例しないことはよく言われるようになりました。とはいえ、1点2点を争ってきた層はまだまだ厚いですから、採用基準や入試方法が変わってもなお、世間に完全に浸透するまでには長い時間がかかるでしょうね。
卓也:なかなか前途多難ですね……。後編では、日本の教育改革に勝算はあるのか、ぜひ希望にあふれた話を聞かせてください、先生!
(後編は5月13日公開予定)
(企画・文:田堂友香子、撮影:今井康一)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら