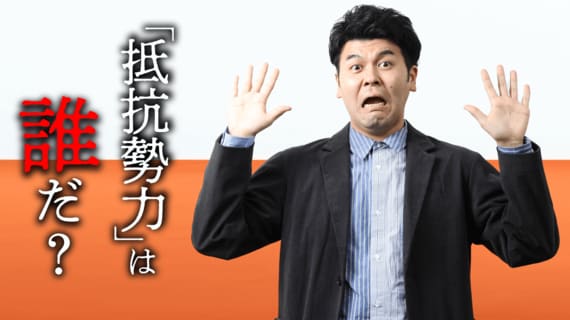
「そんなことも知らないの?」が生まれる悲しい背景

土佐兄弟・卓也(以下、卓也):僕、先生には親を代表して言いたいことや聞きたいことがたくさんあるので、どんどん斬り込ませてもらいます!
ヒロック初等部 校長・蓑手 章吾(以下、蓑手):ええ、忖度せず何でも答えますよ(笑)、よろしくお願いします。僕は大学卒業後、14年間公立小学校で教員をしていました。昨年3月に3校目を辞職し、現在は「ヒロック初等部」という、文部科学省が定めた教育方針とは異なる独自の教育を施すオルタナティブスクールを立ち上げて校長を務めています。
卓也:14年間で3校というと、それぞれの学校に約5年間勤務されたんですね。正直、ずっと同じ学校にいたほうがスムーズな気もしますが、なぜ異動されたんですか?
蓑手:東京都の公立の場合、1つの小学校には最長6年間しかいられないんです。公立は学校間に均一性が求められますから、教員が学校を回ることで各学校の文化を全体に波及させましょう、というのが表向きの理由ですね。でもぶっちゃけ、異動がないほうがめちゃくちゃスムーズです(笑)。とくにつらいのが、同僚や子どもたち、そして保護者と一から信頼関係を築き直すこと。公立の教員にとって異動は当たり前ですが、それでもやりづらいです。
卓也:イメージですが、教育現場って「これはこういうもの」という決まりが多すぎません?例えば「掛け算を教えるのは2年生」とか「3年生に星の動きは教えない」とかは、目の前の子どもの理解度をよそに決まりが先行している気がします。娘の幼稚園では、親の間で「〇〇ちゃんはカタカナが読めるらしい」「〇〇君はもう足し算ができるらしい」といったことが話題になるんです。この先、わが子が挫折感や劣等感を味わうのではと不安な親も多いと思うのですが、児童ごとに適した方法や進度で教育を提供することはできないんでしょうか?

蓑手:一人ひとりに寄り添った教育は、基本的に今の公立小学校では難しいと思います。GIGAスクール構想や1人1台端末が進められているとはいえ、ノウハウの蓄積はいまだ不十分なのが現状でしょう。逆に言えば、カリキュラムが決まっている限り「今年の新入生はカタカナまで書けるから子が多いからひらがなは飛ばそう」ともなりません。そのため、幼稚園から早めに勉強していた子もまた一から学ばければならない。当然、つまらないですよね。すると、彼らを満たすのは知的好奇心ではなく、「俺それ知ってるよ!」「お前そんなことも知らないの?」という優越感になってしまうんですね。
卓也:言ってしまえば、彼らにとって授業は無駄な時間になっているんですね。だからといって学力でクラスを分けるのも違うような……。どうにかできないんですか?
蓑手:僕が注目して実践してきたのが「自由進度学習」です。簡単にいうと、例えば、小6の教室内で小2の掛け算に戻って学んでいる子もいれば、その横で高2や高3の数学に取り組む子もいる、という学習スタイルです。実際に取り入れる学校も増えていて、近年は1人1台端末の普及もありさらに実践しやすくなってきました。しかし、教員の中には「個別では授業の意味がない」「深い理解につながらない」と難色を示す人も多いです。われわれ教員は一斉授業に向けて腕を磨いてきたわけで、そこを否定されると存在自体を否定された気になるのも仕方ないかもしれません。

卓也:それなら先生方には、学習に遅れた子が挫折しないようにケアをしてほしいですね。個人的に、学習面のフォローよりも心理面のフォローが大切だと思うのですが、学校現場にもこうした認識はありますか。































