
いりやま・あきえ●慶応大学大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所を経て、2008年米ピッツバーグ大学経営大学院で博士号取得。2019年から現職。(撮影:尾形文繁)
経営学の観点から見た場合、ソニーの復活はどのように論じることができるのか。『両利きの経営』(東洋経済新報社刊)の監訳・解説を務めた経営学者、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授に解説してもらおう。
1. 知の探索と深化を同時に実現した
経営危機に陥っていた2012年、社長に就任した平井一夫氏には当初「何もやっていないのに高額報酬をもらっている」という批判が集まっていた。だが、私は当時から「平井社長が進んでいる方向は経営学的に理にかなっている」とメディアなどで述べ続けていた。現在の業績改善を見ればそれは間違っていなかったし、平井氏は名経営者として名を残して、今年6月に第一線から退いた。
世界的な経営学の視点で述べれば、平井氏が行ったことの最大のポイントは「知の探索」を取り戻したことにある。知の探索とは人が認知できる範囲を超えて、遠くに認知を広げていく行為のことだ。企業がイノベーションを引き起こす源泉であるといっていい。
例えば平井氏は、14年から「ソニー・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム」、通称SAPという社長直轄の新規事業創出プログラムを始めた。しばしば開発現場にも自ら足を運び、「これいいね、もっと進めよう」などと激励をすることで、エンジニアが失敗を恐れず自由に開発できる雰囲気を作り出したといわれる。まさに「探索」を促していたわけだ。バンド部分に電子機能を組み込んだスマートウォッチの「wena wrist」や、香りを持ち運べる機器の「AROMASTIC」などの新製品はこのプログラムから生まれている。




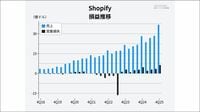































無料会員登録はこちら
ログインはこちら