京都・嵐山の電電宮には電気の神様としてあがめられる電電明神が祭られている。すでに済ませたかもしれないが、JR東日本の経営幹部、担当者らは参拝し、おはらいをしてもらわなければならない。
そう言いたくなるほど、同社は2015年に入って電気にまつわる大きなトラブルを立て続けに起こしている。4月12日に山手線の神田─秋葉原間で架線の支柱が倒壊、4月29日に東北新幹線郡山駅構内で架線が切断され、8月4日には根岸線横浜─桜木町間でも架線が切れた。

こう記すと、鉄道にまつわるトラブルは近年急増したように思われる。だが実態はそうではない。
事故での場合を除いて列車が運休したり、旅客列車に30分以上の遅れが生じたりすることを輸送障害と呼ぶ。国土交通省によると、鉄道係員や車両、鉄道施設に起因する輸送障害の件数は図1のとおりだ。
 拡大する
拡大する
鉄道会社全体が抱える構造的な問題
2014年度はJRと私鉄の合計で1549件であり、1日当たり4.2件起きた計算となる。年間件数も10年度に1395件とやや少なかった点を除くと近年は1500件ほどとあまり変わっていない。要するに、輸送障害は元来多いのだ。

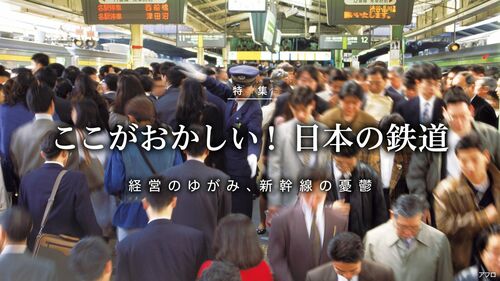































無料会員登録はこちら
ログインはこちら