大学は変われるか「コロナ禍3年」運命の分かれ道、質の高い学びの最適解とは 千葉大学DX加速「オンライン併用で対面」の本気
スマートラーニングセンターの最大の使命は、データ駆動型の教育改革を先導することだ。まずは、さまざまな客観的データを収集、分析し、今後の教育改革の方針の決定に役立てるため、現在運用している学生用のダッシュボード(データを集め、概要をまとめて一覧表示するツール)に加え、教員や学修支援スタッフをはじめとする教務・学務系職員向けのダッシュボードを作り、データを可視化していく。
学生用のダッシュボードには、例えば学修過程と成果を記録したラーニングポートフォリオが蓄積されている。学生自身が学修到達度を確認したり、それをどうキャリアにつなげていくかを考察したりすることに利用するもので、日本でも多くの大学が導入している。だが、教員のティーチングポートフォリオや職員のスタッフポートフォリオを採用する大学はまだ少ない。
「教員同士がチームを組んで授業を展開する集約的学修が増えていくと、相互の授業内容を可視化することは非常に重要な意味を持ってきます。また、個々の学生のニーズに応じたテーラーメイド教育を目指す本学としては、教務・学務系職員が行った学修支援内容を収集、分析することで、教育サービスの質的向上につなげます。ファカルティ・ディベロップメント(FD)、スタッフ・ディベロップメント(SD)の一環にもなるので、ここは重点課題として積極的に取り組みます」
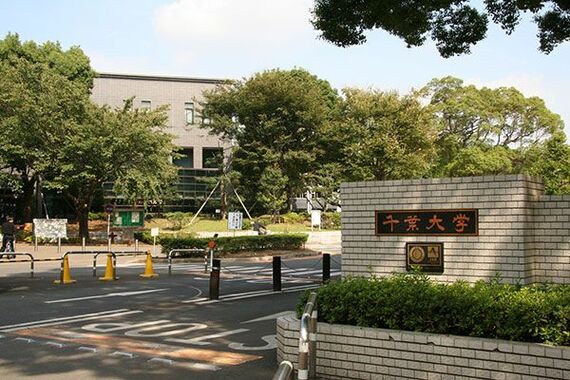
高等教育センターの長に就任するのは、小澤氏だ。歴史学が専門だが、国際教養学部の新設やENGINEプログラムの策定・実施に関わり、全学的な教育改革を牽引してきた。
「DXというと、理学系、情報・IT系の専門家が担当するイメージですが、そういう方たちだけでやっているのでは、定着、普遍化しないと思っています。ですので、私のような人文系の人間がいてもいいのかなという思いで、任に当たっていきます」と決意表明する小澤氏の手腕に期待がかかる。
千葉大は、オンライン授業の積極活用に向けて組織体制を強固にし、今後は大学全体のDXを加速していく。
関連記事
大学が直面、学生は対面より「オンライン授業のほうがいい」の危うさ 芝浦工大が問いただすキャンパスの存在意義
約20年の実践に自信、早稲田大学「オンライン併用の対面授業」推進の真意 ブレンド型の効果大、教員支援に全力を尽くす
(文:田中弘美、写真:すべて千葉大学提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























