灘高コンビが起業「少人数オンライン授業」の魅力 子どもが夢中になるのは「テーマ選び」と、〇〇
講師は灘校や東大関係者など私たちのつながりによって厳選した講師陣を擁しており、博士課程の大学院生や研究者、社会人などが担当しています。2021年8月からサービスを本格スタートし、現在の登録者は約1000人、うち受講者は300人ほどになります。主に小学3~5年生を中心に男女比率は半々、首都圏だけでなく地方や海外の方も受講されています。2回目以降のリピート受講者は60%に達しており、中には3~4カ月の間に30コマも受講されている子どももいます。22年中には月50コマのペースで講座数を拡充しながら、将来的には小学生だけでなく、幼児や中高生も対象としていきたいと考えています。
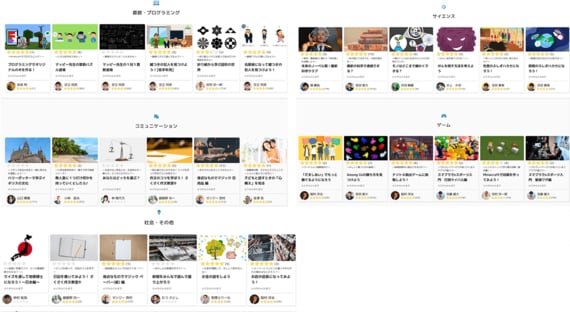
ジャンル別に、学校では学べないようなユニークな切り口のプログラムが並んでいる
――とくに反響のある講座プログラムは何でしょうか。
趙 例えば、人気が高い講座の1つ「知られざる地球の中の世界」というプログラムがあります。こちらは博士課程を修了した研究者の先生が、クイズやゲーム形式を取り入れながら、確かな専門知識を基に授業を行っています。子どもたちも直接、先生と対話しながら授業を受けることができるため、保護者の方からの満足度も高くなっています。とくに私たちは「対話」する授業を重視しており、そのため参加者は1クラス5~6人と設定しています。保護者がそばについていなくても、少人数で対話することにより子どもの集中力が持続され、授業の後にも質問の時間を設けるなど、子どもの知りたいことに細かく対応できるようにしています。こうした点によって、多人数を対象とした録画配信系の動画学習との差別化を図っていきたいと思っています。

“love of learning”(向学心)が広げる子どもの可能性
――「スコラボ」を利用することで、子どもたちにはどんな力を学び取ってほしいと考えていますか。
前田 日本語では“向学心”、英語では、“love of learning”と言われるように、子どもたちには学ぶことを好きになって、主体的に学ぶ力を身に付けてほしいと考えています。もっと言えば、学ぶことを楽しいと思ってほしいのです。そのために「スコラボ」には多数の講座があり、子どもたちは多数の選択肢の中から、好きな講座を選ぶことができるようになっています。好きなものを学べるからこそ、子どもたちは主体的になる。子どもたちが本当に知りたいことをより深く、少人数で教えていく。その結果、向学心が芽生え、自分で学習していく。それがループするようになればいいと思っています。
趙 “love of learning”は好奇心とは異なるものです。好奇心は知れば終わりですが、向学心は「学ぶ過程自体を楽しむもの」です。日本の教育は決まったものを効率的に子どもたちに教えることに特化していますが、私たちは向学心を育むことで子どもの将来の可能性を広げていきたいと考えているのです。
――教育という点でいえば、前田さんは大学から米国で教育を受けていますが、日本の大学教育との大きな違いとは何でしょうか。
前田 教育には「習得」「探究」「活用」という3つの側面がありますが、とくに日本の教育は「習得」に特化しているといえます。そのため、与えられたことをひたすら学習するという能力は高い。例えば、高校卒業の段階で数学の能力が高いのは、日本、韓国、中国など習得型の教育をしている国の生徒となります。その一方、米国では意外にも、MITに入学するような生徒でも数学の能力は全体的にレベルが低く、もしMITの新入生が日本の大学入学共通テストを受ければ、平均点くらいしか取れないでしょう。彼らは高校時代に微分積分も学んでいませんし、私がMITに入学した当初は「こんなにできないの?」と感じたこともあります。
































