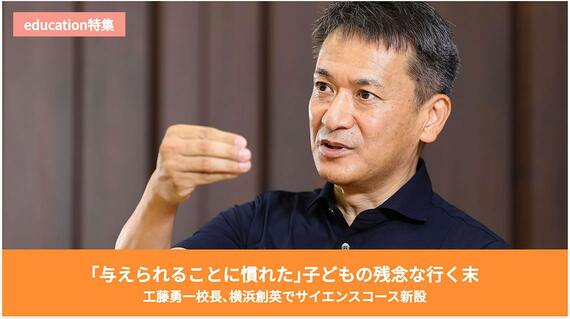GIGA元年、2021年の教育界を人気記事で振り返り 不登校、ブラック校則、偏差値教育、格差まで
ブラック校則があると騒ぎ立てるのは簡単だが、実際に見直すときはどうしたらいいのか、カタリバ では教材やノウハウも提供している。
自己決定しなければ主体性は生まれない
こうした子どもの主体性を育てることは、新しくスタートしている学習指導要領でも大きなキーワードになっている。
麹町中学校の元校長で、現在は横浜創英中学・高等学校校長の工藤勇一氏は、「自ら考え、自己決定しなければ主体性は生まれない」と話す。
工藤氏の動向は、つねに教育関係者の注目の的だが、「今、日本の教育は“サービス提供型”になっている。あれもしなさい、これもしなさいと、子どもたちは過度に手をかけられていて、与えられることに慣れてしまっている。本当に大事なのは、自分で考える力をつけることなのに、学力だけを注視して勉強時間を増やすことが目的になってしまっている」と警鐘を鳴らす。
そこで横浜創英では今、こうした受け身の学び方に一石を投じる、自律した生徒、さらには自律した学校をつくるための改革に取り組んでいる。詳しくは「『与えられることに慣れた』子どもの残念な行く末」を読んでほしい。
なぜ、受け身の学び方から抜け出せないのか。そこには学力や偏差値を重視してきた日本の学歴社会が根本にあるのではないだろうか。
偏差値教育で自信を失った子に光を当てる高校
そんな偏差値教育で自信を失った子、がんじがらめの教育になじめない子の可能性を引き出そうと奮闘する校長がいる。札幌新陽高等学校の荒井優氏だ。「偏差値教育で『自信失った子』伸ばす学校の素顔」では、ソフトバンクの社長室から学校長に転身した民間出身の荒井氏の改革に迫った。
身売り案が出るほど追い込まれていた高校を立て直した経営手腕もさることながら、「今までの学校教育が光を当ててこなかった層に届くような教育をしっかり構築すれば、可能性はある」と、並々ならぬ熱意でユニークな探究型の学びにチャレンジしていた。目指すのは、「本気で挑戦する人の母校」。今後が楽しみな高校の1つだ。
コロナ禍で広がる公立と私立の格差、小学校受験が超人気
一方で、コロナは偏差値教育の象徴とも言うべき受験競争をいっそう過酷にしている。首都圏を中心とする中学受験の過熱化は以前よりいわれてきたが、小学校の受験熱が高まっているのはご存じだろうか。
コロナ禍で公立の小学校が一斉休校となる中、私立小学校はオンラインで授業をいち早く再開させたことなどから、私立に対する信頼が高まった結果と考えられる。「志願倍率10倍超えも『小学校受験』超人気の理由」では、今人気の小学校とその理由、教育の特徴について詳しく取り上げた。
だが、私立の小学校の学費はかなり高い。年間で150万円程度、6年間で1000万円はかかるといわれる。コロナで公立と私立の教育環境の格差が明らかとなったが、私立に行かせることができる家庭なのかどうか、親の収入による教育格差も浮き彫りになってきている。
生まれ育った環境により教育結果に差がある教育格差
教育格差は、教育界のみならず社会全体で向き合うべき課題だ。教育格差とは、生まれ育った環境により学力や最終学歴など教育結果に差があることをいう。コロナ禍の親の収入の減少や休校の影響で、教育格差がいっそう深刻化しているという調査結果もある。
日本について「“生まれ”によって何者にでもなれる可能性が制限されている緩やかな身分社会」と話すのは、早稲田大学准教授の松岡亮二氏だ。教育社会学が専門の松岡氏にインタビューした「『都市vs地方』生まれによる教育格差の深刻度」では、生まれ育った出身地域による差について掘り下げた。
都市出身か、地方出身か、はたまた三大都市圏出身か、非三大都市圏出身かで明らかに最終学歴に差があること、その理由を解説してもらうとともに解決策を探った。すぐに解決できる問題ではないが、一人ひとりの子どもが自分の可能性を追求することのできる社会となるために、多くの人が教育格差の現状を知っておく必要がある。
無意識バイアスがジェンダーギャップを拡大させる
格差を取り上げた記事では、ジェンダーギャップに焦点を当てた「ITやプログラミングから女子中高生が遠のく訳」も非常に読まれた記事だ。