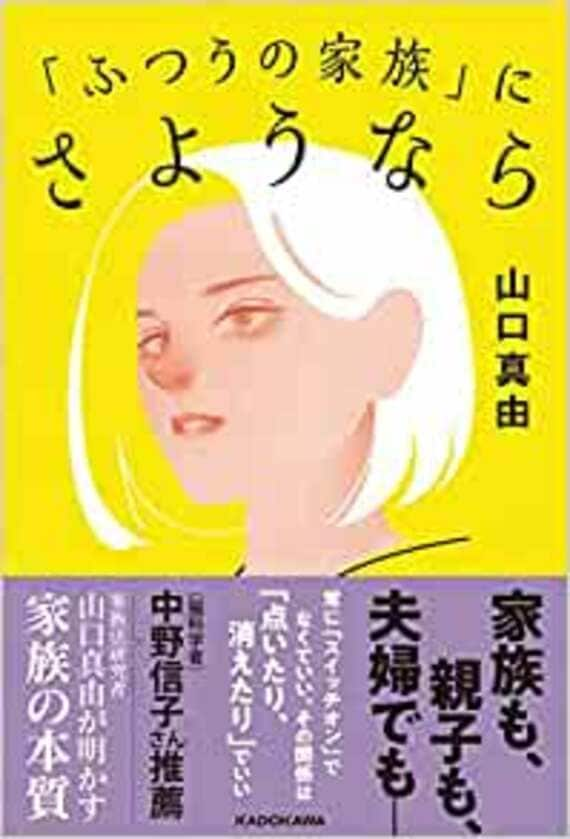老親の事故で子も責任?「家社会」日本の大難題 問われるセーフティーネットの今後のあり方
長男は家族会議の中心となって、父の介護方針を最終的に決定し、自宅以外に多数の不動産や金融資産を保有する父の財産を管理していた。「家」の言葉に言い換えると、認知症になってしまった父から家督を譲られた長男は、家の財産を実質的に管理していたのだ。
そして、家制度の下では、財産は「個人」ではなく「家」に帰属する。だから、家の構成員の責任は、すべからく、その個人ではなく「家」をあて先として請求される。
「個人」ではなく「家」の代表者として責任を問う
事案に当てはめれば、事故を起こした認知症の父が金融資産だけで5000万円超を有する資産家だったとしても、父の資産を含めて家産を管理する家長、すなわち、離れて暮らす息子に責任を問うのだ。彼「個人」ではなくて、「家」の代表者として。
未成年の子どもも認知症の親も区別しない、諸外国と比較して例外的な民法714条の不思議が家制度を前提として鮮やかに解き明かされる。
日本社会においては、長らく「個人」は「家」の中に溶け込んできた。個人を飲み込んで家は連綿と続いていく。逆に、財産は家に帰属するとの制度の下、個人が責任を取る仕組みは日本にはなかった。
江戸時代から200年を経ても、私たちは、いまだに「家」と「個人」の過渡期を生きている。だが、これから社会は、急速に「個人」の時代へと向かっていくだろう。それは単にバラ色の未来ではない。
先ほどの介護の問題からもわかるように、「家」は社会のセーフティーネットを構成して、福祉の一部を担ってきた。数字上で見れば、むしろ、アメリカに次ぐ「低福祉」社会の日本において、なぜか「高福祉」が提供されてきたカラクリはここにある。
「家」が担ってきた経済的なセーフティーネットを、これから、どこの誰が代わって背負ってくれるのか。その答えは、いまだ、存在しない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら