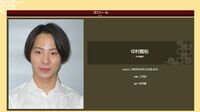教育には伴走者が必要だと痛感した経験です。
学習者にとって、ちょうど良い距離で、一緒に学びに寄り添い、学びを深めていく。
私は、村井研究室で、20年も前にその重要性を体感できたのです。
子どもたち、一人ひとりの学びに伴走するということ
今年、学習指導要領が新しくなりましたが、学校教育も、より一人ひとりに寄り添うことが必要になるでしょう。子どもたちが100人いたら100通りの学び方があり、教科書には書いていない、答えのないようなことも、一緒に探究していかなくてはなりません。
むしろ、すべての知識を先生が教えるのではなく、学びに寄り添って、一緒に知識を深め、必要に応じて、企業や研究者につないであげる。そんなコーディネート能力が求められるようになるかもしれませんね。
――子どもたちの伴走者が、ほかに意識すべきことは何でしょうか。
興味の軸がはっきりしている子に伴走することはとても簡単です。難しいのは、「何が好き?」と聞いても「とくにない」と答える子の興味をいかに引き出すか。
この問題は、本当に難しい。だからこそ私は無理に「何か」をやらなくていいと思っています。今の時代は、「本当の自分は何?」「やりたいことは何?」と、自分にベクトルが向きすぎているんですね。
これから子どもたちが生きていく世界は、正解のない世界。今ない仕事を自分たちでつくり出していくという時代です。
そのような中にあって、大人に何かできるとしたら、性急に「何が好き?」「何がやりたい」と問うのではなく、子どもたちに「生の体験」をさせて、気づきのタネを与えてあげるのがよいのではないでしょうか。
多くの子どもたちに会っていますが、今は、心を揺さぶるような実体験をしている子が少ないと感じます。そうすると、関心の芽も生まれてきません。
――カタリバでもそういう機会を提供している?
はい。現在は新型コロナの影響で、現場に直接行くことは難しいのですが、カタリバオンラインでは、そのような機会を提供しています。

例えば中高生向けに企画している「カタリバオンライン for Teens」では、LGBTで新しい家族の形をつくっている方、東日本大震災で子どもを亡くした大川小学校の児童の遺族、フィリピンにいる、事情があって親と離れ、集団で暮らしている子どもたちなど、多様な人たちと対話をする機会を提供しています。
先日、フィリピンの子どもたちと話した高校生は「なぜこの子たちは、親がいなくてもこんなに明るく元気で頑張っているのに、恵まれた環境にいるはずの私は、自分に自信を持てないのだろう」と話していました。そうした「生の体験」から得られる、自分だけの気づきや疑問が、関心の芽として育ち、ゆくゆくは、その子の未来につながっていくのではないでしょうか。
「オンライン」にもある「貧困」という新たな分断
――オンラインでも学びの機会はつくれるのですね。
はい。ただ、今は子どもたちみんなにパソコンやWi-Fi環境があるわけではありません。「都市」と「地方」だけではなく、オンライン上にも「貧困」という新たな分断があるとわかってきました。そのため、カタリバでは、「あの子にまなびをつなぐ」プロジェクトというものを進めています。