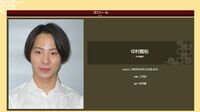はい。大切なのは、高校生であれ大学生などであれ、誰もが多様な環境で生きているということを互いに知ることです。福沢諭吉先生の言葉に「半学半教」という言葉があります。人は誰でも学ぶ立場にも、教える立場にもなれるという意味ですが、お互いにフラットな立場で啓発し合う関係をつくれたら理想的ですね。
子どもたちに必ず伝播する「教師の熱量」
――今村さんご自身は、どのような高校生だったのでしょうか。
私が通っていたのは、岐阜県にある私立の「高山西高校」という学校です。あくまで私の主観ですが、当時は、大学進学クラスが1学年に1クラスだけ、地域のトップ公立高校を落ちた人が、セカンドベストで選ぶ私立高校という印象でした。学力が十分高いわけではなく、クラス全体を覆っている自己肯定感も低いように感じていたことを覚えています。
私自身も、一応大学進学を希望してはいましたが、親も「有名な大学でなければ無理に進学する必要はない」という雰囲気で、ほかの選択肢や可能性を知ることもなく、あまり勉強に熱心ではなかったですね。
――何か変わるきっかけがあったのでしょうか。
生徒たちの雰囲気とは反対に、とにかく、先生方が生徒の夢を一生懸命応援してくれたんです。「大学に行きたい」、生徒がそう決めたなら、徹底的に応援する。もう、それはすごい熱量でした。
今では“ブラック”と言われてしまうかもしれないのですが、朝7時半になると、先生たちが校門前でずらっと待っていてくれるんです。授業の前に単語テストをするために、です。放課後は、小テストの嵐。合格ラインに届かないと夜遅くまで補習です。今でこそ本当に感謝していますが、当時は文句ばかり言っていましたよ。遊びたい年頃ですしね(笑)。
ただ、先生たちの熱意は本物で、それは、私を含めた生徒たちに確実に伝播していき、いつしか「自分もやればできる」「自分でも大学に行けるかもしれない」と希望を持つようになっていきました。
詰め込み型の教育には賛否あると思いますが、あの時期にとことん向き合ってくれた先生方のことは忘れられないですし、今の活動の原体験になっていると感じます。
「インターネットの父」村井純先生に学んだ大切なこと
――教育についての考え方に影響を与えた恩師は、ほかにもいらっしゃいますか。
日本における「インターネットの父」と呼ばれる村井純先生ですね。地方の高校生だった私にとって、日本中どこにいても世界とつながれて、発信者にもなれるインターネットは、まさに“奇跡”でした。そんな“奇跡”の礎を築いたといわれているのが村井先生です。慶応大学に入り、実際に村井先生の元で学べたことは、私にとって大きな財産です。
村井先生の元では、インターネットの理念でもある、互いにフラットでいることの重要性など、さまざまなことを教えていただきました。それだけではなく、学び方の仕組みにおいても、影響を受けたと思います。
当時、研究室には何百人もの学生が所属しており、先生が一人ひとりを見ることは難しかったので、学部生一人ひとりに大学院生がついて育てる “ナナメの仕組み”を取り入れていました。
例えば、論文をうまく書けずに苦労していた私に、先輩が「これはどう思う?」と答えやすいボールを、ほんの少し高い場所から次々に投げてくれる。私はそれに答えることで、自然に視座を高めることができ、自分の言葉をアカデミックに置き換えて、論文を書き上げることができました。