しかし、実際には指導をしてもなかなかうまくはならなかった。就職できるのは、100人中1~2人だった。
「技術はなかなか身につきませんでした。結局、僕らのようにできるようになって、僕らのような暮らしをさせてあげたいというのが目的なんですが、そもそもそれに無理があると考えるようになりました。
彼らは、僕らの100倍努力してようやく就職できるんですね。例えば僕だったら『東大に合格するための勉強プログラム』を強いられているようなものです。そしてどれだけ彼らが努力しても、彼らの技術は一般水準よりずいぶん下になってしまう。必要とされる努力の度合いが全然違うんですよ。そこに差別を感じました」
市販されているものに近い商品制作を目指した場合、どうしても負けてしまう。利用者は非常に苦労するし、教える側も苦労する。
彼らには、彼らにあった仕事があるんじゃないだろうか? と考えるようになった。
「例を示して『こういうふうに作ってください』って頼むより、彼らなりの仕事のよさを見つけようと思うようになりました」
市販の物を作っている場合、軽度の人は手伝いができるが、それができない人がいる。
木を削ってと頼むと、木がなくなるまで削り取ってしまう。布を真っ直ぐ縫わず、縫って縫ってひとかたまりにしてしまう。
工芸としては価値がなくてもアートとして通用
「そのような作業では機能性のある売れる商品にはならないから、規格品を作って売る場合は全然ダメなんです。でも、それがなんとなく自由で楽しくて、面白いと感じるようになりました。

売れない作品が少しずつ生まれ始め、そのうちにそういう作品をアートの公募展に出してみたんです。そうしたら工芸としては価値がなくても、アートとしては通用することがわかりました。そこでようやく
『アートって面白いよね』
って気づいたんですね」
一時期は、学園を離れて家具屋として独立しようか? と考えたこともあったが、利用者の作品が面白いと感じたのをきっかけに、学園に残ろうと思った。
福森さんが34~35歳の頃だった。
元々やっていた企業の下請けを徐々に撤廃していき、その代わりにオリジナルの作品を生み出し始めた。
だんだん作品が認められていくことによって、利用者を見る人々の目に尊敬の念がこもる。たとえ障害が重くても
「尊敬されている」
という眼差しは感じると福森さんは考える。そういう眼差しが積み重なって、自分が認められていると感じたら、きっと「ホッ」と生きやすくなるんじゃないか? と思う。



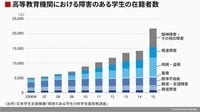



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら