貧乏人の経済学 もういちど貧困問題を根っこから考える アビジット・V・バナジー、エスター・デュフロ著/山形浩生訳 ~貧困解消は選択の論理の理解から
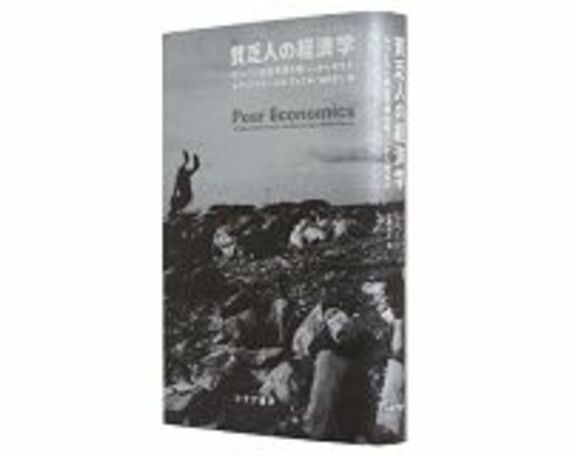
貧乏な人たちの本当のことは、先進国で豊かに暮らす私たちにはわからない。実際、多くの人は貧困と聞けば饑餓を連想する。だから、貧乏な人たちにおカネをあげれば真っ先にカロリーが高く栄養豊富な食糧を買うのが当然だ、と思い込んでいる。しかし、途上国の最貧家庭ではおカネをもらうと、主食になるイモやコメよりも副食のエビや肉、あるいはアルコールなどの嗜好品を優先して買うという。そんな行動を見て、おカネではなく現物で援助するほうが効果的だとか、そもそも援助自体に意味はないといった侃々諤々(かんかんがくがく)の“論争”を繰り返しても、現実の貧困は解消できない。
貧乏な人たちは確かに空腹だが、イモやコメよりも買いたいものは沢山ある。カロリーや栄養を削っても欲望を満たそうとするのはむしろ人間として自然な選択である。主食優先で体力をつけ、一所懸命に働いてより多くのおカネを稼げるなら目先の欲望を抑えるくらいの自制心は、貧乏な人たちだって備えている。だが、そうした割のよい働く機会から排除されている最貧層の人たちは、カロリーと栄養を摂って厳しい労働に耐える身体をつくっても、再び空腹になるのを待つ以外に身体を活かすことはできないのだ。
その意味で貧乏な人たちは経済的に非合理でもなければ、誘惑に弱い怠け者でもない。与えられた条件の下で合理的に行動しているにすぎない。問題があるとすれば、そうした選択は子どもたちには必ずしも合理的でないことだ。もし貧乏な親が子どもの健康や将来のために時間とおカネを割くなら、子どもは親よりもずっとよい暮らしを営めるようになる。重要なのは貧しい親を持った子どもの未来をよりよくするためにどんな政策が有効かを発見する試行錯誤であり、経済援助の是非を問う大上段の議論ではない。






























