文科省が「就職氷河期世代の積極採用」を通知、"ゆくゆくは教師になりたいと思っている人"どのくらいいる?学校現場でほしいのは「こんな人」
「トラブルの際も、40代の教員が対応することで保護者の印象が変わることもあります。また、営業経験者ならプレゼンのスキルを授業に活かせるでしょうし、コーチング力のある人や新人教育経験がある人は生徒指導に活かせるはず。40〜50代は若手の頃からパソコンを使っていますから、ITスキルをもたらすこともあるでしょう。
実際、私もパソコントラブルがあると必ず呼ばれていました。ただ、教員の仕事はいきなり深いプールに入って初めて泳ぎを教えられるようなもの。フォームがおかしくても泳げていると判断されるところがあります。校務支援システムや保護者対応などのガイダンスが事前にあればずいぶん違うのでは」
近藤氏は他県への移住を機に教職を離れることになったが、「教員は本来とてもすばらしい仕事。職場環境が整い、多くの人が教育の世界に入っていってくれたら」と話す。
近藤氏の言葉を表すデータもある。OECDの調査によれば、日本はほかの職業の人と比べて教員の仕事の満足度が高く、世界でもトップクラスだ。ただ、社会がその「やりがい」に大きく依存してきた部分もあったとも言える。
氷河期世代の積極採用と働き方改革を同時に
今年8月、文科省は26年度予算案の概算要求に、「2028年度に向けた3万人の定数改善計画」を盛り込んだことが話題となった。文科省が掲げた「新たな『定数改善計画』の策定」が実現するのか、それが中長期的な教員定数改善につながるのか。氷河期世代を含む社会人教員の話にとどまらず、正規教職員の採用増加にも影響すると見られる。
なお、氷河期世代の積極採用を促進する教育職員政策課は、教員の養成・採用から働き方改革まで総合的に担う部署として新設された。その課長を務める大江氏はこう語る。
「先般の給特法の改正を受けて2029年までに教員の時間外在校時間を月30時間まで減らすことになりました。近年は減少していますが、TALISの調査では日本の教員の仕事時間は世界一です。文科省でも、自治体と膝を突き合わせて残業計画について直接話すといった個別の支援体制で教員の働き方改革に取り組んでいます」
文科省として部活の地域移行、定数改善、多様な人材の確保など、あらゆる取り組みを総動員しながら、これまで以上に踏み込んで働き方改革を進めるという。
就職氷河期から20年以上が経ち、学校を取り巻く環境は大きく変わった。ほかの分野で生きてきた熱意ある氷河期世代を学校に呼び込むことができるのか、どんな効果が生まれるのか。今後に期待したい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

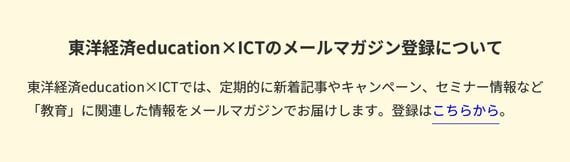

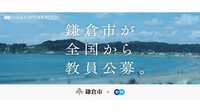






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら