文科省が「就職氷河期世代の積極採用」を通知、"ゆくゆくは教師になりたいと思っている人"どのくらいいる?学校現場でほしいのは「こんな人」
また、TOEICやTOEFLの点数に応じて英語実技試験を免除する、国際レベルの芸術コンクール入賞者や競技大会出場者・指導者に一部試験免除または加点を行うといった自治体もある。つまり、誰にどんな一部試験免除や加点を行うかは、「そもそもその自治体がどんな人材を求めているか」が大前提となるのだ。
では氷河期世代を含む未経験者には、どんな役割が期待されているのだろうか。
「学校以外での豊富な経験を提供していただけるのではと考えています。年齢的な均衡の観点からも、多様な専門性を持つ教師集団で特定の年代だけがいないのは不自然な状態だと言えます」
未経験者が学校現場で活躍するには支援も必要だ。ただ、任命権とともに研修の実施義務も自治体にあるため、文科省は教職員支援機構が提供する教職未経験者向けのオンデマンド教材などの活用を推進している。
「すでに対策をとっている自治体も多く、23年度の時点で、都道府県と政令市などを合わせた68自治体のうち、50自治体の教育委員会では、実務経験のない教員免許保有者向け研修を実施しています」
しかし、氷河期世代はすでに40代から50代。学校現場に求められる豊かな経験を持つ人は、ほかの分野で自分の居場所を見つけているのではないか。
「ゆくゆくは教師になりたいと思っていた人がほかの分野で活躍してから教員になった例も聞きますので、一概には言えないと考えています。就職氷河期に、教職への熱意もありながら採用に至らずに他の道を選ばざるを得なかった人が再び教職を目指して入職いただくことは意義深いこと。先般の閣僚会議で総理から指示いただいているので、それも踏まえた社会人教師の促進を一層行っていきたいと考えています」
当事者が語る氷河期世代の役割と可能性
国や文科省のこうした動きに対し、「いい試みだと思う」と話すのは氷河期世代の近藤裕佑氏(44歳)だ。近藤氏は教員を目指していたが、採用枠の少なさから民間への就職にシフトチェンジ。教育事業に15年間携わったのち、公立中学校の教員となった。
「現場は定年間近のベテランと20〜30代の若手がほとんど。両者を結ぶ主任クラスの年齢層がいませんでした。同僚はいい人ばかりでしたが、組織のあり方や働き方、価値観が昭和のままで、民間とのギャップを感じました」
未経験の氷河期世代が学校にもたらす可能性についてこう話す。

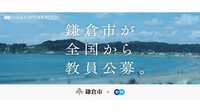






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら