「吹奏楽コンクール」今の仕組みは"昭和"のまま?何十年も見過ごされてきた「音楽理論の欠如」、期待される<指導者の"読譜力"向上>
このように「理論的要素」を明確にせず「“感性のみ”の価値観」のままであるコンクールは、もはや「オワコン」になる方向に突き進むといっても過言ではない。
今やテクノロジーの進化によってガンダムのモビルスーツのような人間機能拡張装置が現実的な実用段階に入っているように、多くの分野においてはいかに論理性と感性のシナジーを生むかというフェーズに入っているにもかかわらず、吹奏楽の世界はいまだに音楽理論が欠如しており、よくも悪くも昭和のままなのである。
ゆえに私は、これまでも吹奏楽指導者の音楽的基礎力の不十分さについて指摘してきた。指導者のクラシック音楽としての基礎能力(和声・対位法・ソルフェージュ等)が、演奏者の能力進化に追いついていないのでは、と思わざるをえないのである。
冒頭で述べた、すでに多くの人が指摘しているコンクール課題曲の問題やレパートリーの質的な危惧の根幹も指導者の読譜能力の低さにあると強く推量される。
また、少子化の中での部活動の地域展開は、地域・世代・団体ごとの距離を狭める協働体制を作ることによって、子どもと大人の異なる価値観のシナジーによる「文化濃縮」という考え方をベースにする必要がある。そのためにも、大人の再勉強が不可欠なのではないだろうか。
基礎力の向上を怠れば「文化の衰退」を招く
学校の教科書では、例えば国語に名文が掲載され、理系科目には極めてベーシックな要素からの教えの構築がなされているからこそ、子どもたちはその基礎の上に計り知れない創造性を発揮しているはずである。
その点、吹奏楽はどうか。これだけ従事人口を保持しているにもかかわらず、理論にあたる音楽的基礎力が不十分な状況が何十年も続いている。食事が体を作るように、学問は人間の脳の栄養である。音楽も同様であり、よい音楽作品を見極める審美眼を鍛えることを怠ってしまうことは、すなわち文化の衰退を招くことになる。
部活動の出口を見ても明らかではないだろうか。これだけ盛んな吹奏楽において、吹奏楽部での熱心な活動がプロフェッショナルの道につながるケースは極めて少ない。野球やサッカーなどと比べると、その差は歴然である。やはり「基礎力の向上」がアップデートされていないことに起因するのであろう。
私たちは今、文化としての吹奏楽の「進化」と「衰退」の分水嶺にいる。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

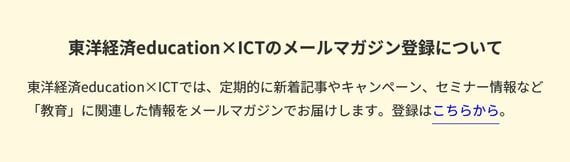
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら