なぜ、引き算は苦手なのか?
今回は比較的わかりやすい、イメージしやすい書写、毛筆とそろばんを取り上げたが、ほかにも学習指導要領や教科書の内容として、もっと優先順位を下げてもいいのではないか、と議論したほうがよいことはあると思う。
実際、NPO法人School Voice Projectが教員向けに実施したアンケート調査(2024年12月~25年2月)でも、これは減らしてもいいのでは、という意見がたくさんあがっている(ほかの例としては、算数でのヘクタールの扱いなど)。
私は、小学校では特別活動の中のクラブ活動(中学校などの部活動とは性格が異なる)で、毛筆やそろばんをやれるところはやったらよい、と思う。そろばんはそれほどの時間数ではないが、書写や漢字の書き取りが少なくなれば、年間数十時間生み出せる。
文科省という役所は、足し算はするのに引き算は苦手だな、と思う。だが、文科省だけの責任とするのも酷かもしれない。文科省には、これを学習指導要領や教科書に入れてくれ、といった陳情が相次いでいるという。さまざまな業界団体等から、ときには政治家と一緒に。何かを減らそうものなら、さまざまな人たちや団体が猛反対するだろう。その調整コスト、労力は大変なものである。
しかも、学習指導要領は教科ごとに専門家が集まって審議する。先ほどの論点整理は横断的な話なので、教科ごとではないが、現在はこの論点整理をベースとしつつ、各教科でのワーキンググループでの検討がスタートしている。
だが、専門家であればあるほど、思い入れがあるし、引き算はなかなかできない。それに専門分化は細かくなされていて、他人の領域には軽々には口を出さない。例えば、仮に漢文の専門家が「小学校で毛筆までやらせなくてもいいのでは?」などと居酒屋談義ならまだしも、国の審議会で発言しようものなら、「漢文だって必要なんですか?」という議論を誘発しかねないだろう。だから、みな黙る。
もちろん、専門家へのリスペクトは大事にしたい。今回の私の寄稿は、書写等の専門家から見れば、乱暴な議論に見えるところもあろうかと思う。だが、専門家ならば、もう少し社会にわかりやすく必要性などを説得的に示す必要があるのではないか。
子どもの時間だって有限だ。小学生で、毎日のように6時間目まで授業を受けて、しんどい子だって少なくない。もう少し減らすなり、選択制を広げるべきではないだろうか(関連記事:小学生から「ほぼ毎日6時間授業」でいいのか、子どもと先生の本音とあるべき姿 「定時に帰れない、授業準備できない」悲痛な声)。
少なくとも、もう少し優先度を落としてもいいことは、何なのか、という検討、議論を排除するべきではない。大人の都合で、子どもの時間をたくさん奪ってはいけない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


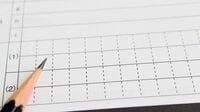
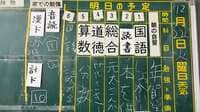




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら