今回の論点整理で「情報活用能力」について多く記載されているように、これだけインターネットやAIが普及、便利になってきている中、情報リテラシーや活用力を培うことなどは、これまでに増して重要となっている。
これはおそらく多くの人が賛同するのではないかと思う(子どものスマホ利用やSNSとの関わりなど各論には賛否あるが)。しかし、だからといって、学習内容を増やしてばかりだと、どんどん教科書は厚くなっていくし、子どもたちの中にはアップアップになる子もでてくる。
小学生に書写やそろばんは必須なのか?
では、減らせることはないのだろうか。いくつか例を挙げよう。現行の小学校の学習指導要領では、全学年で書写の時間を設けることが定められている。また、3年生以上では毛筆を使用することとなっており、「各学年年間30単位時間程度を配当する」とまで明記されている(小学校学習指導要領p.40)。
2024年には、奈良教育大学附属小学校で、長年毛筆による指導が行われていなかったことが問題視されたが、たしかに現行の指導要領では毛筆は必須となっている。だが、これからの指導要領で、果たして本当にどれほど必要なのだろうか。なお、今回は小学校を中心に論じるが、書写は中学校でも必修となっている。
そもそも、書写の授業は何のためにあるのか。現行の学習指導要領では、3・4年生について、次のとおり記載している。
(ア) 文字の組立て方を理解し,形を整えて書くこと。
(イ) 漢字や仮名の大きさ,配列に注意して書くこと。
(ウ) 毛筆を使用して点画の書き方への理解を深め,筆圧などに注意して書くこと。
(出所)小学校学習指導要領p.32, 33
硯と筆しかなかった江戸時代ならまだしも、1人1台端末も普及した今の小学校において、文字の形を整えて、配列に注意して書くこと、あるいは筆圧に注意して書くことが、どれほど重要なのだろうか。
素人目には理解できない。関連して、小学校で膨大な時間を費やしている漢字の書き取りや正しく書けるかどうかといったチェックも、もっと減らしてよいと、私は考えている。
似た話として、いまだ小学校の算数でそろばんについても記載されている。3年生と4年生のところに記載があるが、以下は3年生についてだ。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ア) そろばんによる数の表し方について知ること。
(イ) 簡単な加法及び減法の計算の仕方について知り,計算すること。
イ 次のような思考力,判断力,表現力等を身に付けること。
(ア) そろばんの仕組みに着目し,大きな数や小数の計算の仕方を考えること。
(出所)小学校学習指導要領p.73, 74
私は、書写はもとより国語教育については専門外だし、そろばんや算数教育についても素人だ。ぜひ、専門家と文科省から、ご説明いただきたいと思うが、少なくとも次の3点について検討する必要がある。

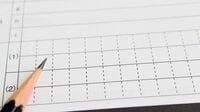
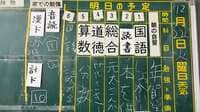




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら