労組の傘に守られない人は労働者の8割強。中央組織・連合の存在意義は、いかにして彼らの権利を守れるかにある。

労働組合は何のためにあるのか。一人の労働者単独の力では経営者・使用者に立ち向かえない、そのために労組は生まれた。だが日本全体でみれば、労組という傘に守られていない人は労働者の8割強にもなる。労組の中央組織である連合の存在意義は、いかにその人たちの権利を守り、働きがいを高めていけるかにあるといえよう。
連合は電話などの労働相談窓口を常設している。昔からある不当解雇、賃金未払い、サービス残業などに加え、最近では、パワハラ、セクハラ、マタハラなどハラスメント関係や、フリーランスからの相談も多い。辞めたくても辞めさせてくれないという学生バイトからの相談には、世相を感じる。そんな時代に労組の役割は、「見て見ぬふりはしない」ということに尽きる。

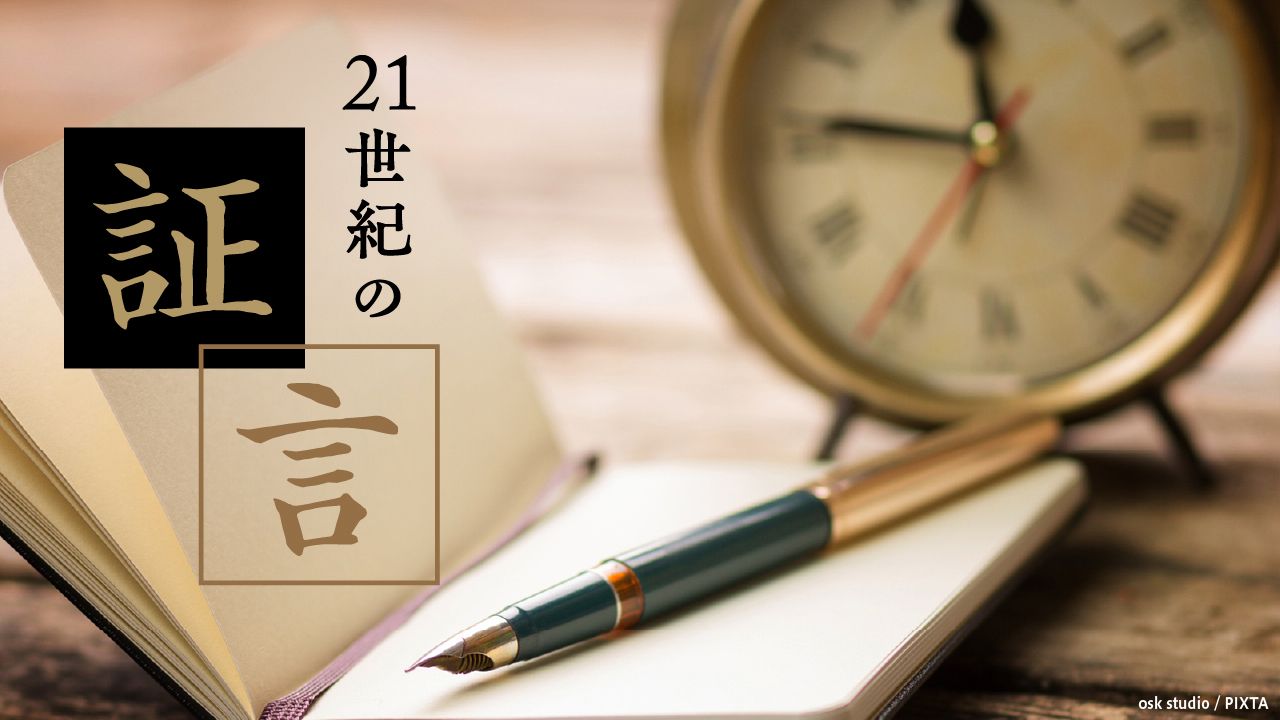






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら