なぜあの学校や自治体はうまくいく?苫野一徳が語る「学びの構造転換」超秘訣 「何のための教育か?」見落とされがちな本質論

今起きている、「日本教育史上初の現象」とは?
――「みんなで同じことを同じペースで同じようなやり方で学ぶスタイル」から「個別化・協同化・プロジェクト化の融合」へと変わっていくべきだという、「学びの構造転換」を提唱されています。最近、まさに個別最適な学びや協働的な学びを目指して教育改革に取り組む学校や自治体が増えていますが、「学びの構造転換」はどれくらい進んだと思われますか。
2014年の拙書『教育の力』(講談社現代新書)にも、「学びの構造転換」の中・長期的ビジョンを描きましたが、個別化と協同化の融合が進み、プロジェクト化の充実に至るまでには、あと15~20年くらいかかるのではないかと思っています。
しかし、この10年ほどでその一歩は力強く踏み出されたと感じています。例えば自由進度学習などにチャレンジする先生が増えましたし、とくに自治体規模で「学びの構造転換」に取り組むところがいくつも出てきました。
――注目されている自治体をご紹介ください。
広島県は2014年と早い時期から「学びの変革」に着手しています。名古屋市も2019年度から個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を推進する「ナゴヤ スクール イノベーション」に全市で取り組んでいて、プロジェクト型学習やイエナプランを参考にした独自の授業改革に挑戦する学校が出てきています。
加賀市や芦屋市も2023年度に新たな教育ビジョンを策定して学びの構造転換を進めているところです。富山市はイエナプラン的教育を市内の多くの学校で取り入れ始めており、生駒市も大きく動き始めています。
――公教育の本質は「自由の相互承認(※)」の実質化にあるということも繰り返し強調されてきましたが、生駒市の「第3次 生駒市教育大綱」には「自由の相互承認の感性を育む」といった言葉が記されましたね。
※自由に生きたいと願っている存在同士であることをお互いに認め合うこと
はい、生駒市の教育大綱づくりのときに教育委員会でお話しさせていただいたのがまさに「自由の相互承認」でした。
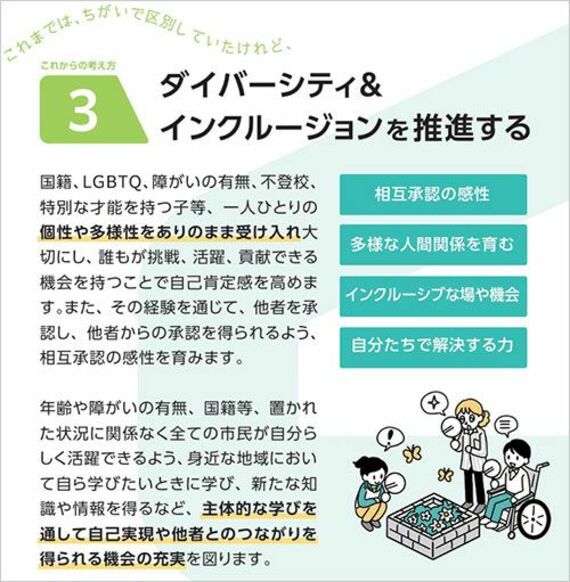
実は岐阜市でも2020年改訂の教育大綱に「自由の相互承認の感度を育む」という言葉が記載されています。学びの多様化学校の先駆けとなった草潤中学校の設置なども含めて、岐阜市も改革に積極的な自治体だと思います。
また、岐阜といえば本巣市も教育改革に力を入れており、根尾学園という全校40人程の義務教育学校では異年齢の対話を大事にしたり、市内の子どもたちがみんなで市の「子どもの権利条例」の土台となる「こども憲章」を作ったりしてきました。
長野県の伊那小学校や愛知県の緒川小学校のように、何十年も前から「学びの個別化・共同化・プロジェクト化」に取り組んできた公立学校はあるのですが、そうした実践は先生方や学校単位の頑張りで何とか進められてきたケースが多いです。
そこを複数の自治体が率先して取り組み始めたというのは、おそらく日本教育史上初の現象です。さらにすばらしいことに、そうした自治体同士はだいたいつながりあっているんですよね。知を共有したり支え合ったりできるので、連携は本当に大事なこと。この動きがどこかの時点で閾値を超え、全国的な構造転換へと進んでいくことを期待しています。






























