会費の不正利用が多発「PTAの金」問題の根本原因、学校への寄付にも要注意 P連でも使途不明金…健全な運営に必要なこと
「学校には『PTAに頼んだら(PTA会費で)学校の備品などを買ってもらえる』、PTAも『学校から頼まれたら買ってあげないと』という、昔ながらの慣習のようなものが背景にあると捉えています。しかし、この問題の根底には、学校教育法の『設置者負担の原則』、地方財政法における『住民負担の禁止』という2つの法的な側面が大きく関わっています」
学校教育法第5条では、空調設備や学校家具をはじめとする備品など、学校運営や教育活動に係る経費は、原則として設置者=学校負担となっている。
また、地方財政法第4条の5では、「国(中略)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない」とある。つまり、PTAが学校に寄付することは、法的に問題となる可能性があるということだ。
「『PTA側から自発的に学校に寄付したい』という場合は、自治体が定める関係規定に従い『寄附採納』の手続きをふめば寄付が可能になりますが、任意加入のPTAである(=集金の同意がある)こととあわせて、PTA総会で会員の総意を得るなどが必要です。このことも含め、PTA会費による学校への安易な寄付は法律に抵触する可能性があること、さらに、学校においては、制服やシューズにかかる入学準備費など、学校徴収金として予算化されず見えにくい保護者の教育費負担など『学校としてのお金の問題』が存在することも、知っておく必要があると思います」
PTA会費が、学校の裁量により給食費未納分の補填に
PTA会費の使われ方について、関東地方に住む保護者から驚くべき情報が寄せられた。「PTA会費が、学校の裁量により、給食費や教材費といった学校徴収金の補填に使われていた」というのだ。
2024年4月から子どもが通う小学校のPTA会長になった岩井利枝子氏(仮名)は、こう言う。
「新しくPTA会長に就任し、引き継ぎの際に昨年度の会計簿を見たら、気になる支出がありました。その支出の摘要欄を見ると、『給食費未納分の補填』と書いてあったのです」(岩井さん、以下同)
未納金をPTA会費で補填し、年度会計を締結していたことが発覚したのだ。岩井氏は続ける。
「さらに驚いたのは、PTA会費の通帳管理は学校側が行っており、PTA会長の承認なしにお金が出せる状況だったのです。決算の承認についても、校長先生、教頭先生が押印するスペースはあるのにPTA会長の押印スペースがありませんでした。PTA会費なのに、PTA会長の承認なしに、学校の裁量でお金が出せる状況だったことが明らかになったのです」
岩井氏によると、前任のPTA会長や会計担当者は未納金補填について気づかず、過去の会計でも同様の処理が行われていた可能性が高いという。
「前任の会長さんも会計さんも、くじ引きで仕方なく活動していた方とのこと。やらされている人がやると、『最低限のことだけしておしまいにしたい』という気持ちからチェックがおざなりになるもわからなくないですが、学校側がPTA会費の通帳管理を行い、会長の承認なしにお金を出せる状況はどう考えても不適切であると思います。今年度は、学校と対話を重ねながら、会計処理の不正を防ぐ体制を整備することはもちろん、PTAのあり方、PTA会費の見直しなどを行っていきたいと思います」
「お金のかからないPTA活動」を
学校のPTAとお金をめぐる問題を改善していくためには、どのような方法があるのだろうか。
栁澤氏は、さまざまな不正行為や寄付問題などの根底にあるのは、「PTA会費の存在そのもの」だと指摘する。
「PTA会費は、必要な活動資金を確保するための手段であって、活動の目的ではありません。『なぜPTA会費を集めるのか』という原点に立ち返り、PTA活動を“会費ベース”ではなく“活動ベース”で考える。例えば、僕が関わってきたPTAでは、これまでの会費ありきの活動を見直して規約を改正し、ここ10年くらい、その年ごとに活動に必要なお金を会員数で割ってPTA会費を決めています。年会費はその年により異なり、1000円から2000円くらいですが、300円まで削減された年もあります。


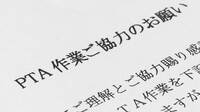




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら