吹奏楽「働き方改革や地域移行」の荒波くぐり、短い練習で子どもを伸ばすには 楽しみながら「自主性育む」運営ノウハウは
オザワ部長:カレーに例えると、味が出てきますね(笑)。バンドにはさまざまなレベルの方がいらっしゃると思いますが、先生のレシピに沿って練習すると、みなさん同様に上達できるのでしょうか。
石田:3カ月もすれば、学年が上の先輩に追いつくことができますよ。ただ、飽きっぽい人は続かないです。そんなことやる暇あったら曲の練習したほうがいいと固定観念を持っている人も上手になりません(笑)。
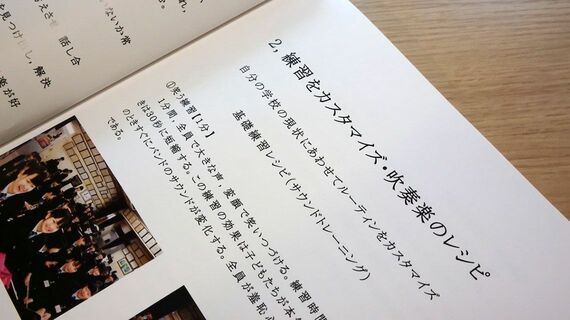
レシピ全体を通して私が重要視しているのが、実践のペア練習です。
例えば、先生と生徒、または先輩が後輩とペアを組んで教えるとしますよね。腕組みしてそこはこうだよと言葉で説明して聞かせるよりも、何も喋らずにメトロノームだけ鳴らして実際に吹いてみせることが大事です。
生徒や後輩にも同じ音を同じ長さで吹いてもらって、音の周波数や波形を見るオシロスコープ、音量をデシベルで表示するサウンドメーターなどを用いて音の違いを比べます。教える側は数値で違いを把握できますし、生徒は音を聞いてまねて、感覚的によい音の出し方をつかんできます。
オザワ部長:1対1で人をまねてうまくなっていくと。音楽は英会話みたいなものなんですね。一昔前の日本の英語教育のように、理屈で文法だけ教えても一向に話せるようにならないのと同じように感じました。
石田:おっしゃる通り! 音楽と言語は同じです。私は幼少期から父親の転勤の関係でいろんな場所に住んできましたが、住むと現地の言葉に慣れて、いつの間にかイントネーションが変わります。なじむのは早くて、子どもは1週間もかからないです。また、友達が話している時に被せて話すことはしないように、音楽も、同時に吹くより、1人ずつ回して吹いて、他人の音をよく聞いてまねたほうがすぐに上達します。
オザワ部長:バンドの中でのペア練習というのは上達度が高い人と低い人がペアですか。
石田:そうです。さらに曲の練習をする際にポイントになるのが、同じ楽器同士ではなく、同じフレーズやモチーフを吹いている人同士で練習することです。このことを私はパートではなく、パーツと呼んでいます。
開智アカデミックはパート練習よりもパーツ練習を多くしています。曲作りは、一緒に100回演奏するよりも、同じフレーズを1人ずつ順番に吹いて、それを30回繰り返したほうが上達します。
「短時間練習は生徒の自主性を育む」デジタルツールも有効活用
オザワ部長:先ほどメンバーの方にもお話を少し伺いましたが、コンクールに向けた練習では、1人ずつ順番に音を吹いていったり、指導用鍵盤であるハーモニーディレクターを使って音合わせをしたりすることが多かったようですね。
石田:開智アカデミックでは、そうした練習計画をすべて学生が作って実行しています。学生指揮者として練習計画を立てる人(各学年、金管・木管・打楽器から1人ずつ、全員で12人)が、組み合わせ練習表(フレーズごとにチーム分けしたもの)を作ってペア練習しています。中学校は先生がすべて計画してしまうことが多いですが、本来は中学生でも自分たちで運営していける力を持っていますよ。
オザワ部長:生徒に任せる部分を見極めることで、教員の働き方改革にもつながりますね。子どもたちの自主性も育まれるように思います。






























