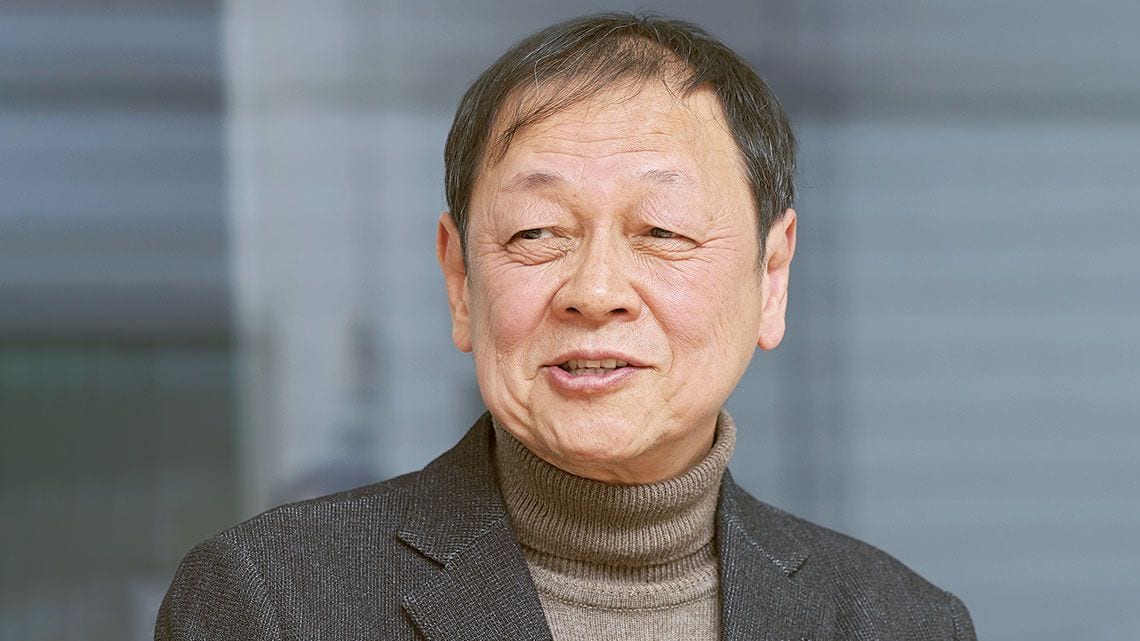
――初開催から20年を経た今、「M-1」誕生の舞台裏を書こうと思ったきっかけは。
とくに何かの節目ということではなく、単純に声をかけていただいたので。これまでもブログに書評を書いたり、大阪の文学学校に通って芸人を主人公にした小説を書いたりはしてきたけど、ノンフィクションとして「M-1」を書く発想はなかった。打診されてみて初めて「それも面白いな」と思いました。
ただ、書き始めてみると難しかったですね。小説と違って実名がばんばん出るし、事実を曲げて書くことはできない。当たり前のことと思って書いた部分が編集者にまったく伝わらず、「お笑い界」だけの常識なのだと知ることも多かった。関西と関東、地域による感覚の違いもあったかもしれません。
意外だった、若手の「やりたい」
──本書には漫才復興に向けたプロジェクトの紆余曲折が細かく描かれています。精神的に最もこたえた時期はどのあたりでしたか。
やっぱり最初の、(役員に呼び出され)「1人でやれ」と言われた直後でしたね。社内的に誰も注目していない、かつ漫才師もそんなに熱心にやっているようには見えない漫才を立て直すというのはきつかった。「M-1」開催という目標ができたことで、やっといろいろ本格的に動き始めました。
その後も、スポンサーが見つからない、放送してくれるテレビ局が見つからない、参加者が増えないといったつらい場面はけっこうありました。めげなかったのには、(島田)紳助さんの存在が大きかった。終始一緒に動いたわけでもなかったけど、後ろ盾でいてくれたことで、訳のわからん自信のようなものを持てました。



































無料会員登録はこちら
ログインはこちら