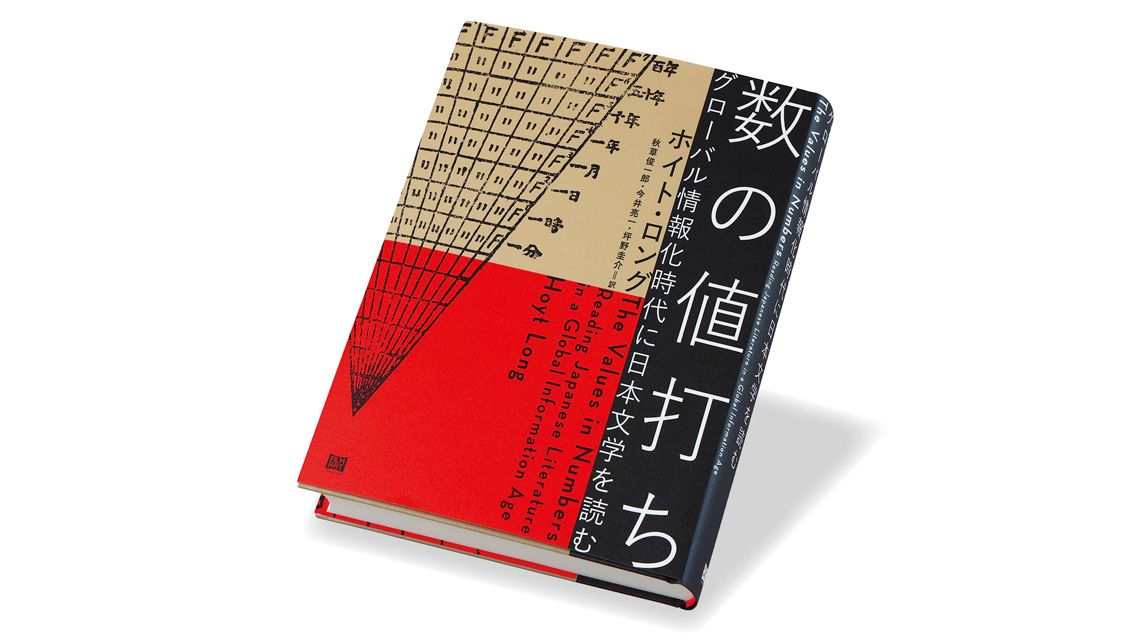
数の値打ち グローバル情報化時代に日本文学を読む(ホイト・ロング 著/秋草俊一郎、今井亮一、坪野圭介 訳/フィルムアート社/4400円/432ページ)
[著者プロフィル]Hoyt Long/1976年生まれ。米オレゴン大学卒業後、米ミシガン大学で博士号取得。近代日本文学を専門とし、現在、米シカゴ大学東アジア言語文化研究科教授。シカゴ・テキスト・ラボを主宰している。著書に『平らでない地面の上』(未邦訳)がある。
リズム、句法などの形式が決まっている短歌や俳句は、その文化を共有する人たちの中で、何が短歌や俳句に当たるかの共通理解がある。しかし、より自由に書かれる散文はどうだろう。例えば論説と随筆の違いはどこにあるのか。あるいは、文学作品とされるものとそうでないものはどう区別されるのか。
文学作品の新しい「読み」
本書は、ジャンルを超えた大量のテキストをコンピューターで分析し、複数の作品に共通する構造を明らかにしつつ、文学作品の新しい「読み」を提供する。特定の文脈の下で読むべき本が決まりそれを精密に読む、という伝統的な手法ではなく、同時代の大量のテキストから作品の位置づけを理解し、それに基づいて個々の作品を読んでいくのだ。
トピックボードAD
有料会員限定記事

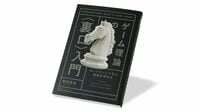
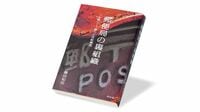
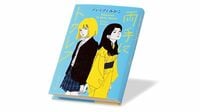




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら