処方と遺伝子検査はセットが望ましいが、日本では未整備だ。

レカネマブは点滴で、約1時間かけて投与する(写真:エーザイ)
「薬がない」。こんな言葉が医療現場で当たり前のように聞かれるようになって久しい。『週刊東洋経済』の10月10日発売号(10月14日号)は「薬クライシス」を特集。供給不安の深層を製薬メーカーと薬局の両方から浮き彫りにします。
米国に続き、日本でも9月25日に承認されたアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」。認知症の進行自体を遅らせる効果を持つ薬としては国内初で、年内にも発売される見込みだ。アルツハイマー病患者や家族の期待は高まっている。
しかし認知症専門医にとっては、積極的に投与したい薬とはいえないようだ。その理由の1つが、「ARIA(アリア)」と呼ばれる副作用の存在だ。
ARIAとは、脳の浮腫や微小な出血などを指す。多くの人は無症状だが、まれにけいれんやてんかんなどの重篤な症状が出ることがある。まだわかっていないことも多いが、レカネマブの臨床試験(治験)の結果からは、特定の遺伝子タイプでこの症状が現れやすいことが判明した。
想定していなかった遺伝子検査の推奨
トピックボードAD
有料会員限定記事

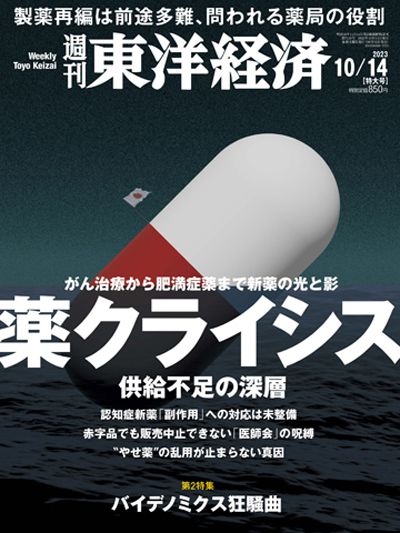
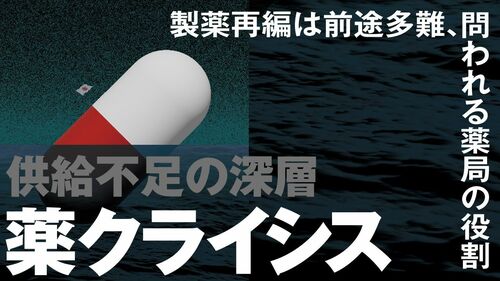
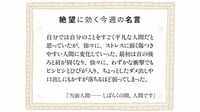






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら