学習指導案とは?作り方や役割、計画の立て方を解説

学習指導案とは?
学習指導案とは、授業において、授業者が生徒に伝えるべきことや進め方について具体的かつ詳細に記した学習指導の計画書のことです。年間指導計画書に基づいて、指導内容や学習活動、評価項目を記します。
授業をどのような学習形態で行い(グループワーク、調べ学習など)、どのような順序で指導し、またどのように生徒を評価するかについて、一定の形式にまとめたものといえます。
学習指導案の役割
学習指導案の役割としては、次の3つが挙げられます。
1:実際に授業を展開するうえでの進行表
先述したように、学習指導案は授業者が当該授業で伝えるべき内容を具体的かつ詳細に記した計画書です。指導案を基に授業を行うことで、ねらいに即した学習指導を効率的に進めることができます。
2:授業研究の資料
公開授業では、参観者に対して授業のねらいや工夫点など、授業者の意図を伝える必要があり、学習指導案はそのための資料としても役立ちます。生徒観や指導観など共通理解を図るためにも重要です。
3:授業の記録
授業終了後、振り返って生徒の反応や計画の成果、課題点を明らかにする授業記録としての役割もあります。この記録を基に考察することで授業の質を向上させ、ひいては学校全体の教育の質の維持・向上につながります。
学習指導案の作り方
では実際に学習指導案を作る場合、どのように進めていけばいいのでしょうか。順序立てて解説します。
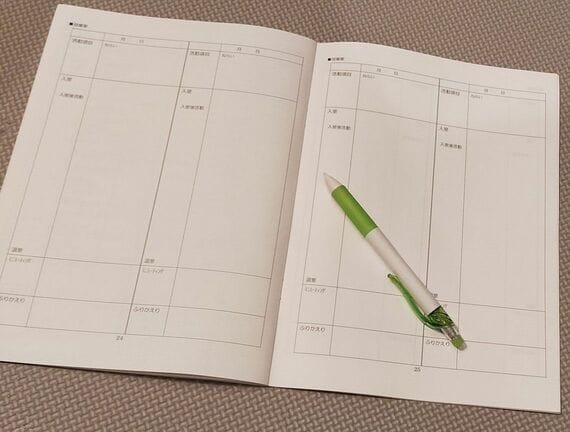
テーマを決める
まずは教科書のどの単元で授業をするのかを決めます。年度初めに決定しているシラバスがあればそれに基づいて決めましょう。「教科書〇ページから〇ページ」のように具体的に記します。
時間や場所を設定する
授業の日時や場所について、「〇月〇日〇曜日 △限 〇年〇組教室」のように具体的に記します。
学習目標の設定に必要な情報を把握する
単元の学習の中で生徒にどのような力を身に付けさせたいのかという視点から、授業の目標を設定します。学習指導要領などを参考にしながら、そのために必要な情報を集めましょう。
学習指導案の構成要素を決める
学習指導案の構成要素は、校種や学年などによって変わってきますが、基本的には以下で構成されています。
2:単元設定の理由
(1) 教材観
(2) 生徒観
(3) 指導観
3:単元の目標
4:単元の評価規準
5:単元の指導計画
6:本時案
(1) 目標
(2) 評価
(3) 展開
実施計画を立てる
構成要素の項目をまとめて、具体的な授業の実施計画を立てていきます。
学習指導案作成のポイント
学習指導案の形式はそれぞれの学校によって変わりますが、構成要素の中でも特に重要となるポイントがあります。具体的には以下のとおりです。
単元設定の理由
生徒観を踏まえ、単元の特徴、身に付けさせたい力について具体的に記します。また、既習単元との関連、その単元を取り上げることの意義や価値を明確にします。
2:生徒観
これまで生徒がどのような学習を行ってきたか、どのような実態なのかを踏まえてこの単元で身に付けさせたい力について授業者の立場で具体的に記します。
3:指導観
生徒観と教材観を踏まえた学習課題を克服するための具体的な指導・支援の方法を記します。また、指導形態や環境設定、主体的な学びに向けた指導上の工夫や方法を明確にします。






























