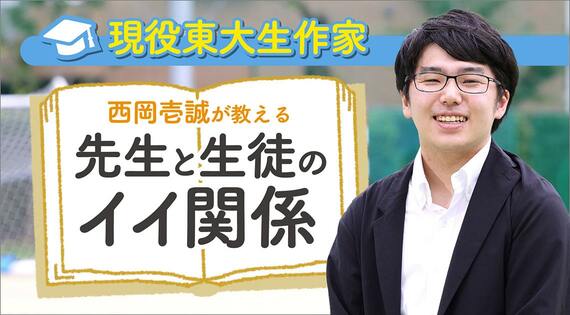しかしこのテーマであれば、多くの学生が「自分のこと」として捉えることができます。自分の生の経験に立脚した意見のほうが、面白みがあって、多くの人にとって示唆的なものになるのです。
例えば、本企画に参加してくれた高校生の意見をいくつか紹介すると、Kさんは「SNSによって、自分の評価が多くの場所で行われるようになり、自分に自信を持つのが難しくなっている」ということを指摘してくれました。これは高校生ならではの視点ですね。また、Hさんは「学校内の定期テストや模試などで、相対的な評価が何度も行われていて、どうしても他人と比較する習慣がついてしまっているのではないか」ということを指摘してくれました。Iさんも同様に、「日本は学歴社会で、いい大学に行けなければ不幸になる、という感覚があり、若者がこのことについて考える際には『5年後に自分がいい大学に入れているのかどうか』が気になってしまって点数を低くしてしまうのではないか」ということを指摘してくれました。どの意見も、その人ならではの考え方ですよね。こういった等身大の意見のほうが、多くの人にとってプラスの気づきを与えるものになると思います。
さて、この記事を読んでいるのが先生や指導者の方であれば、この記事でシェアさせていただきたいのは「まず、学生に自分事として捉えてもらえるようなテーマから練習してもらうと効果が出やすい」ということです。大きすぎる社会問題の話ではなく、もっと分解してその人に近しいテーマにすることも重要でしょう。
例えば、「情報プライバシーについて」というテーマでなく、「SNSに人の顔写真をアップデートすることを法的に規制するべきかどうか」のように、学生が日常的に触れているテーマからスタートするようにするのがお勧めです。その人が触れやすいテーマを選ぶ必要があるということですね。
この記事を読んでいるのが生徒の方やこれから小論文対策をする方であれば、まずは小論文と作文の違いを理解したうえで、「自分の」意見が求められるからこそ「自分の経験」「自分の感覚」といったものも大事にしてもらいたい、ということを伝えたいです。
あくまでも主語は「あなた自身」なので、「あなた」としての意見をつくるよう意識することを忘れてはいけないのだと思います。ぜひ皆さん、参考にしてもらえればと思います。
(注記のない写真:KazuA / PIXTA)
執筆:西岡壱誠
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら