「経営ありきの変革はしない」就職率1位の東京家政大に「女子大離れ」を聞く イメージ先行?「女子大不要論」の裏にあるもの
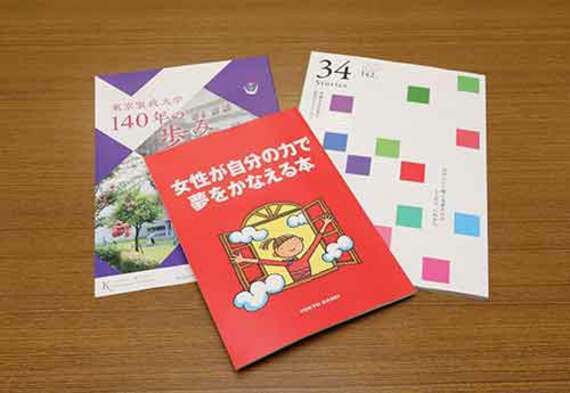
近年、都市部では受験の低年齢化が進んでいる。とくに中学校受験では大学選びの志向に反して、男女別学のメリットが見直されてもいる。まだ性別による発達の差が大きい年齢であることや、思春期に異性の目を気にせず伸び伸び過ごせることなどがその要因だが、女子生徒にとっては「女子校のほうがリーダーを経験できる確率が上がる」ということも挙げられる。まだまだ社会には女性のリーダーが少なく、最新の日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中116位と低い。これは先進国の中で最低レベルであると知っている人も多いだろう。
「女性の就業促進や活躍を後押しするために新たな法律が作られましたが、その後もずっと同じ話がされているなと思っています」
岩井氏は、2015年に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」にそう言及して苦笑した。
「経済的自立を目的に、女性の手に職を、という発想で立ち上がった女子大は多く、本学もその先駆けの1つ。創設者の熱い思いを感じています。家事や育児は男性も一緒にやるものだ、という考え方の男性が増えてきて、協力して生活を営む風潮が生まれているのはいいことです。しかしそれは生活面に限ったことで、広く社会を見ると、仕事の面ではまだまだ男女平等とは言えません。共学でも女子大でも、自分が学びたいことを学べるのならどちらだっていいですよね。でもその本質を置き去りにして漫然と『共学がいい』と考えるなら、おそらくそれはイメージにすぎないと思うのです」
「家政」という分野に「女のやること」というイメージを持ち、女子大より共学のほうが何となく有利だと考える人が多数派を占める状況は、女子大が目指す社会像が実現されているとはいえないだろう。今語られる女子大不要論の裏には、まだ女子大が必要であることを裏付ける不均衡こそが隠れているのかもしれない。
(文:鈴木絢子、撮影:尾形文繁)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























