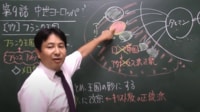「歴史総合」でも未だ危機的な過積載、かぎ握る大学入試には高大連携が不可欠 世界史部分と日本史部分で教員交代の残念さ
教員と生徒は共に「対等な探究者(歴史実践者)」となる
”考える歴史”の魅力について小川氏は、ファクトをつないで因果関係を自分で解釈したり、その意義づけをしたりすることができる市民を育てることになると言う。
例えば、「近代化」の過程で欧米や日本では旧体制が打倒され、自由の理念が重視されて立憲主義に移行したが、同時に植民地の人々や奴隷の自由を認めない人種主義が広がった。物事を単純な善悪や進歩のプロセスで捉えるのではなく、さまざまなファクトに目を配り、そこから多面的で相互につながっている歴史の姿を繊細に見ていくと、これをどう解釈して、どう意義づけるかはとてもスリリングなテーマになる。そして、この歴史が自分にとってどのような意味を持っているのかを考えると切実さが増してくる。こうした授業を実現させるには、中学校の社会科との連携も必要だ。小川氏が言う。
「歴史の流れを大きく把握することや、対話をしながら学ぶことについては、これまで中学校の歴史教育が努力してきたことです。そうであれば、むしろ高校の教員が、中学校の教育手法に学ぶところも大きいのでは。ただし、中学の社会科歴史分野は圧倒的に日本史中心で世界史の流れがほとんど見えてきません。真の「総合」とは何か。中学でどこまで考えて、どこから先を高校で考えるべきかを今後、高校も中学も共に考えていくべきでしょう」
そして、世間が注目しているであろう大学入試問題との連携は、現在どのような方向に向かっているのだろうか。
「重箱の隅をつつくような悪問をなくしていくことは、大学側も共通認識として持っているはずです。大学共通テストの出題も、歴史を単なる暗記ではなく、資料を基に知識を活用し、多面的・多角的に歴史を読み解いていく方向に変わり始めています。ただ、思考力を問う問題や採点は、受験生にとっても大学にとっても大きな負担です。少子化が進む今、大学入試は学生を落とすものから、より能力を引き出すものへと変化が求められています。これからの出題は、大学側でも試行錯誤が続くでしょう」
まだ始まったばかりであるがゆえに可能性も課題もある歴史総合。今後、課題を解決しながら前進するポイントは何か。小川氏はこう指摘した。
「第1は、現場の教員が過積載の教科書を精選して歴史の大きな流れを大切にすること。第2に、大学入試において、知識偏重の出題がなされないように高校と大学でもっと議論すること。第3は、考える歴史に転換するために、『考える授業』について教員間での交流や事例集めをするということです。そのうえで教員は生徒を『対等な探究者(歴史実践者)』としてリスペクトし、教員と生徒が共に正解のない歴史の課題を考えるという意識を持つべきでしょう。歴史について考え対話をするときに、生徒の思考から学ぶことが、私はしょっちゅうあります。私たち教員にとって、歴史総合はやりがいのある仕事なのです」
(文:國貞 文隆、編集部 田堂友香子、注記のない写真:Mai / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら