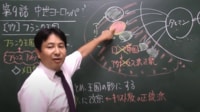「歴史総合」でも未だ危機的な過積載、かぎ握る大学入試には高大連携が不可欠 世界史部分と日本史部分で教員交代の残念さ

「嫌われた世界史」は生まれ変われるのか
2022年度から必履修科目となった「歴史総合」。その特徴は知識よりも思考力を重視することにあるが、これまでと大きく異なる点は、生徒が授業で近現代の日本史と世界史を統合的に学習することにある。文字どおり、国内外の歴史を合わせて総合的に学ぶわけだが、なぜ今、新科目が必要となったのか。23年6月刊行の『歴史総合を学ぶ③世界史とは何か:「歴史実践」のために』など岩波新書の『シリーズ歴史総合を学ぶ』の執筆者でもある世界史教員の小川幸司氏はこう語る。

長野県伊那弥生ヶ丘高等学校教諭
長野県立高校や県教育委員会などに勤務、中央教育審議会の社会・地歴公民ワーキンググループの専門委員も務める。長野県蘇南高等学校校長を経て、23年4月から現職。著書に『世界史との対話』全3巻(地歴社)、『岩波講座世界歴史01 世界史とは何か』(岩波書店)の編集委員も務めた
(写真は東洋経済撮影)
「議論の発端は、いわゆる世界史未履修問題です。世界史は1989年の学習指導要領改訂で必履修科目になりました。当時の問題意識は、グローバル化の時代に対応できる若者を育成するというものです。しかし生徒側も教員側も、世界史は覚えることが膨大で学びにくい科目という認識があり、進学校を中心に世界史は『やったことにして』、日本史や地理を重点的に学ぶという事例が続発したのです」
一方で、東京都や神奈川県では必履修科目に選ばれなかった日本史が独自に必修化されたり、地理も必修にしようという声が高まったりするなどの動きが出始める。そして2011年、歴史研究者からなる日本学術会議の史学委員会にて、日本史と世界史を合わせて近現代史を中心に学ぶべきだという議論が起こった。並行して、中教審の初等中等教育分科会でも歴史教育のあり方が検討された結果、歴史については「歴史総合」、地理は「地理総合」、そして「現代社会」を引き継いだ「公共」の3つを必履修科目にすることが16年に打ち出されたのだ。
「世界史は日本史を除いた、いわば外国史です。高校生にとって本来、世界のことがわかる魅力的な科目なのですが、年々歴史研究が進み、覚えるべき知識が増え、入試も難問化していきました。歴史総合は、改めて基礎的な歴史学習とは何かを考える中で生まれたのです」
こうして22年度に必履修化された歴史総合は、これまでの教授内容重視(コンテンツベース)から、資質・能力重視(コンピテンシーベース)の授業へ生まれ変わったのだが、具体的に歴史総合が求める資質・能力は何を指すのだろう。