子ども・若手教員にメリット大、富山県南砺市「全市でチーム担任制」の深い狙い 5年間で退職ゼロ「初任者教員の定着」でも成果

学校の硬直化の原因?「そんなことしていいんですか」
富山県の南砺市では2020年4月、市内のすべての公立小中学校でチーム担任制を導入した。現在は小学校8校・中学校7校・義務教育学校1校で同制度が運用されている。革新的な選択には、抜き差しならない地域の事情があった。19年に南砺市教育委員会の教育長に就任した松本謙一氏は語る。
「南砺市は4町4村が合併し誕生した市で、山間部から平野部まで広大な面積を有し、他市に比べ少子高齢化が進んでいます。小学校は半世紀前に大規模な統合を終えており、ほとんどの旧町村が小・中1校ずつとなっています。現在、急速に過疎化が進んでいますが、これ以上の統合があると地域それぞれの文化が失われてしまいます。小規模校の利点も考慮し、各地域に学校を残すという方針を決めました」
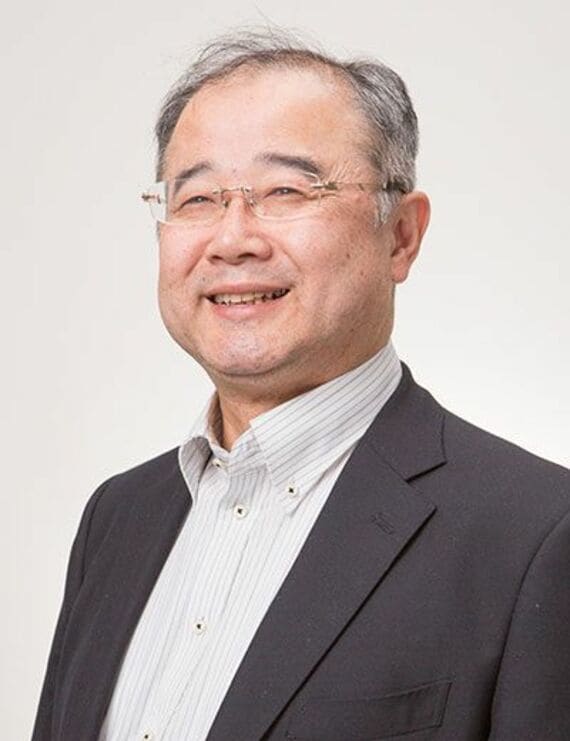
松本謙一(まつもと・けんいち)
南砺市出身。小学校で16年間、中学校で4年間教員として教えたのち、富山県教育委員会指導主事、富山大学教授、金沢大学大学院教授などを経て、2019年4月から現職。富山大学名誉教授、日本生活科・総合的学習教育学会顧問
(写真:南砺市教育委員会提供)
松本氏は「教員の大量採用と大量退職によって、教育の質が低下すること」も懸念していた。南砺市のチーム担任制(1学級1担任とする従来の学級運営の方法を見直し、複数の教員がチームで学級運営にかかわる体制)で目指すのは「小規模校のよさを生かして、持続可能な教育基盤をつくること」だ。例えば1学年1学級の小学校では、学習指導要領の目標が2学年ごとに設定されている音楽科や道徳科などにおいて、1・2年生、3・4年生が一緒に授業を行う。とくに実技教科は教員の得手不得手の差も大きいため、互いに補い合うこともできるだろう。チームがベテラン教員と若手教員の組み合わせになれば、必然的にOJTも可能になる。主担当を分担すれば、1人がメインで教える授業は単純に考えて2分の1になる。その分1つの授業研究にかけられる時間が増え、その質が高められるはずだと松本氏は言う。
子どもたちにとっても、サポートに回る教員の存在は授業の理解度を深めるだろう。教員との接点が増えれば、学習以外の場面で相談したいことがあるときにも、気軽に教員に話しかけることができるようになる。また、「生活ノート」を複数の教員の目で見ることで、子どもの変化を発見できる可能性が高くなる。保護者対応も必ず2人で当たるようにしているため、若手教員にとっては授業外でも先輩教員の手腕を間近で見られる格好の機会になる。






























