森山良子さん&松井五郎さんによる校歌も話題の臼田小、統合への道のり 増える学校統合「反対の声や課題」どう向き合う
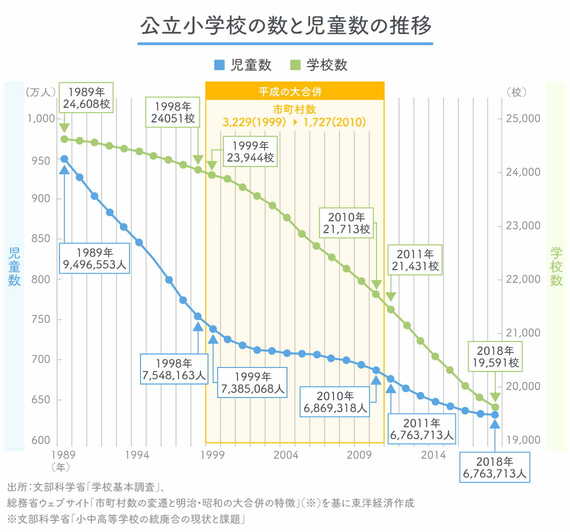
地域住民が抱く「自分の町から学校がなくなる寂しさ」
佐久市の場合、統合に至った4校の状況は必ずしも同じではなかった。2022年度末の時点で、旧臼田小と田口小の児童数は各230人ほど。減少を続けてはいたが、まだある程度の規模を保てていた。一方で山間部に位置する青沼小と切原小の児童数は各100人を切っており、最も少ない青沼小では50人ほどになっていた。これでは当然、地域住民の切迫感にも差が出る。旧臼田小と田口小の保護者は、当初はどちらかというと反対派のほうが多かったと井出氏は語る。
「当初は『数が少ない青沼小と切原小が統合すればいい』という意見や、『青沼小と田口小など、距離の近い2校だけで一緒になってはどうか』という声も多く聞かれました。でもそれでは、早晩また同じ問題が持ち上がると予想されました。20年、30年というスパンで見て、子どもたちと地域の未来を考えたとき、やはりこのタイミングで地域の4校を統合するべきだということになったのです」

それでも根強い反対の声はあった。4校統合を検討する委員会の委員長に、反対意見を直接伝えにくる住民もいたという。
「例えば田口小は長野県の五稜郭である龍岡城跡にあり、全国的にも珍しい立地のため地域でも愛されていました。ほかにもそれぞれの小学校に特徴があり、地域の文化拠点にもなっていました。それだけに、学校に起因する地域住民の誇りや支持も強かったのだと思います。本校の統合に対してどう理解を得たのかといえば、最終的には『のんでいただいた』という言い方が正確だと思います。性急に進めずに根気強く議論を行ってきたこと、子どものためであることを伝え続けて共感してもらったこと。この2点に尽きるのではないでしょうか」
全国で相次ぐ学校の統廃合では、反対運動が報じられることも少なくない。「自分の町から学校がなくなる寂しさ、受け入れられない気持ちはよくわかる」と、井出氏は反対派の人々にも心を寄せる。
「地域の方の声を受け止めて、不安や寂しさを解消することにも努めていきたいし、新しい学校を再び『自分たちの学校』だと感じてもらいたい。とくに統合を経た学校は、地域と学校の互恵性を築くことを大切にするべきだと思います」
その言葉どおり、井出氏は学校が地域の力を借りたり、反対に地域の力になったりする取り組みを構想中だ。例えばコミュニティ・スクールの機能を充実させたり、コーラスや書道、絵画など、地域の人の生涯学習の場をつくったり。学校と地域を相互に開かれたものにしていきたいと考えている。
多様な地域の教育素材が集まったことを「好機」と捉えて
統合によって臼田小に生まれた課題として、スクールバスにまつわることが挙げられる。学区が大きく広がったため、臼田小の子どもたちの約4割は、市教育委員会が用意したスクールバスで通学している。これについて井出氏は「スクールバス運行による学校運営の難しさがある」と感じている。






























