少子化と統廃合で減る公立小「へき地教育」の斬新 小規模校をメリットに変えるICT先進事例

適正規模に満たない小規模校の今
学力の向上だけでなく、集団の中で多様な価値観に触れ、互いに協力しながら切磋琢磨し、社会性を身に付ける場所。それが学校だ。
そのため、公立の小学校や中学校には適正規模の基準が設けられている。しかし、山間部や島などでは統廃合で適正規模を維持することが難しい。また、学校は地域の要でもあることから、小規模校・過小規模校として存続するケースも少なくない。文部科学省でも2015年から小規模校のメリットを最大化し、デメリットを最小化させるための取り組みを推進している。
こうした動きが起こる以前から、小規模校の教育に取り組んできた北海道教育大学 へき地・小規模校教育研究センターでは、21年11月に「第19回へき地・小規模校教育推進フォーラム2021」を開催。日本各地から集まった4名のパネリストがへき地や小規模校の課題を解決するICT活用の先進事例を発表した。

(写真:第19回へき地・小規模校教育推進フォーラム2021より)
学校管理下のSNSで児童が得たもの
「ICT活用の先進事例はへき地・小規模校から始まっているものが多い」
こう話すのは、自身も山間地域の中学校で社会科教諭として勤務した経験を持つ、和歌山大学 教育学部教職大学院教授の豊田充崇氏だ。
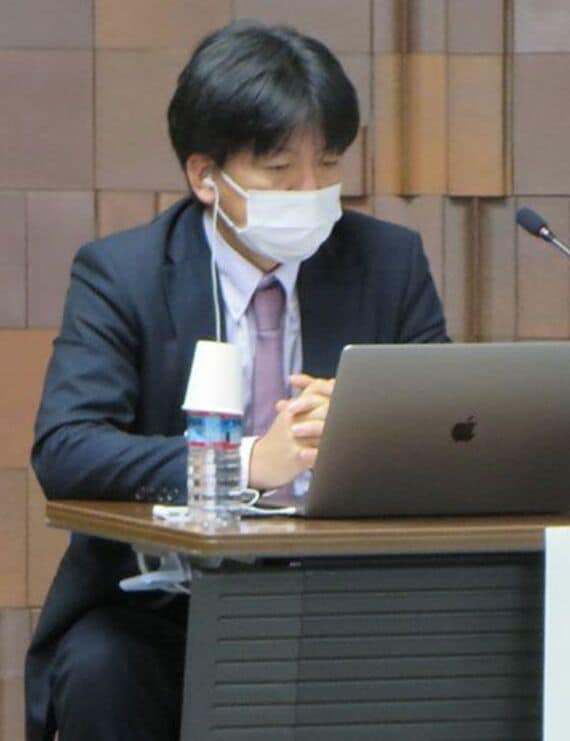
和歌山大学
教育学部教職大学院 教授
(写真:第19回へき地・小規模校教育推進フォーラム2021より)
豊田氏によると、和歌山県は県庁所在地にも複式学級を持つ学校があり、県内全域に小規模校が点在する。10年からは県とインテル、研究者の協業で「T21プロジェクト」を実施。1人1台端末で学校間の交流のほか、学校の管理下で学習目的のSNSを使い、へき地の小・中学校と大学の教育学部生がバーチャル学級を構築するなど、ICT活用事例を蓄積してきた。
「極小規模校では、先生も友達も家族のような存在。学級新聞などを作っても、見てくれる人が限られてしまいます。しかし、SNSを通じて外部の人に読んでもらい、コメントをもらうことで児童は創作意欲をかき立てられ、敬語や社会性を学ぶことができるのです」(豊田氏)






























