海外に比べ「いじめ」が増える日本、決定的に欠けている「エビデンス」の視点 欧米で成功している予防の8割は「傍観者教育」
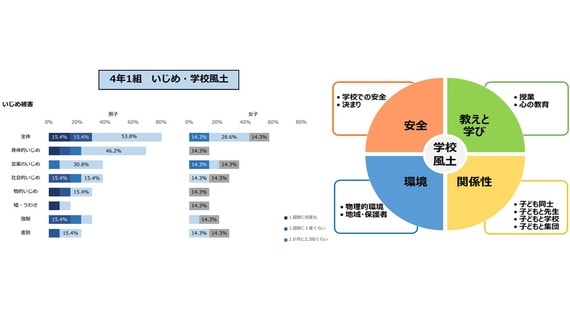
海外に比べ、日本のいじめが減らない理由とは?
文科省調査によると、2021年度のいじめの認知件数は61万5351件と過去最多を記録した。子どもの発達科学研究所所長の和久田学氏は、「とくに重大事態の件数が705件と前回調査から37%増えている点から深刻な状況にあるといえます」と指摘し、海外の現状についてこう語る。

公益社団法人子どもの発達科学研究所所長・主席研究員
静岡大学教育学部卒業。特別支援学校教諭として20年以上現場で勤め、その後科学的根拠のある支援方法や、発達障害、問題行動に関する研究をするために連合大学院で学び、小児発達学の博士学位を取得。2012年より現職、子どもの問題行動(いじめや不登校・暴力行為)の予防・介入支援に関するプログラム・支援者トレーニング・教材の開発に取り組む。大阪大学大学院招聘教員、日本児童青年精神医学会 教育に関する委員会 委員。著書に『学校を変える いじめの科学』(日本評論社)など
「海外ではいじめの研究が進んでおり、例えば米国では学校での銃乱射事件の背景にいじめの問題が隠れていることも多いので、予防策が熱心に研究されてきました。現在、世界のいじめの研究で主流となっている領域は『インターネット』『LGBTQ』『職場』で、実は『学校』に関しては対策がある程度明らかになっています。実際、われわれの研究所の調査でも、いじめの件数が確実に減っている国は多い。一方、日本のいじめは増えています」
この違いは、エビデンスに基づいた対応を行っているかどうかにあると和久田氏は言う。
「エビデンスとは、背景に行動科学や疫学統計学、脳科学などの科学的根拠があり、再現性が担保できること。海外では教育にもエビデンスを取り入れています。医療と同様に、教育も子どもの命を預かっている現場である以上、日本も教員の経験則や勘に頼るのではなく、科学的に裏付けされた成功確率の高い手法を取り入れるべきではないでしょうか」
和久田氏によると、欧米で成功しているいじめ予防プログラムの8割は「傍観者教育」だという。
「複数の研究で、いじめには約8割の傍観者がいることがわかっています。例えば1990年代のカナダの研究では、いじめ事案の85%に傍観者が存在していました。また、そのうち74%は加害者側に、23%は被害者側についていましたが、実は傍観者の約80%がいじめを嫌だと感じていた。さらに、13%の傍観者がいじめを止めようとしたところ、57%のいじめが数秒以内に止まったといいます。また、教員がいじめの現場にいたケースは13%と、いじめを教員が見つけるのは難しいことも明らかになっています。いじめを見つける努力をするよりも、日頃からいじめに関する正しい知識や行動を教えるほうが、子どもが傷つく機会をはるかに減らせるということです」






























