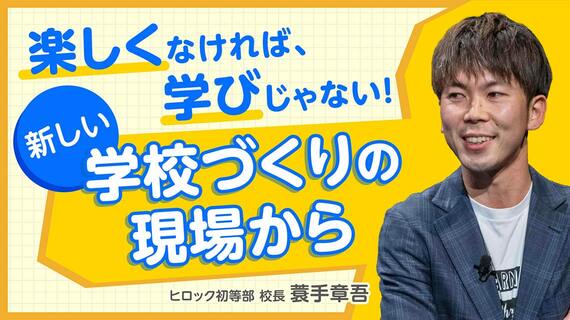3つ目は、偏差値を上げるなど学校内外から成果が強く求められていること。ほとんどの学校は、単元の終わりや学期末に行う試験を基に通知表を作成し、家庭に報告しています。テストの点数や通知表の結果がよくないと、子どもは親に叱られるかもしれませんが、同じように教員や学校に対しても苦情が寄せられます。授業や教え方がよくないのではないか、もっと手厚くフォローしてほしい、居残りやプリントをたくさん出すべきだ……などです。受験などが関わる学年になってくると、比例して要望もエスカレートしていきます。
「社会を生き抜く力が伸びる」企業連携を推し進める方策とは
企業との連携事業を行うことで、社会を生き抜く力は大きく伸びると思います。しかし、それが目の前のペーパーテストにすぐに結び付くかというと、そうならないものが多いのもまた事実です。
子どもたちは楽しみながら力も付けたはずなのに、暗記する時間が減ったためにテストの点数が下がった……なんていう悲痛な声も耳にします。学習を理解できるようにしてあげたいという気持ちは教員も同じですが、同じくらい「親から責められたくない」「苦情を受け入れることで、これ以上仕事を増やしたくない」という気持ちもあるのではないでしょうか。

以上のように、学校現場も苦しい中で、なかなか期待に応えられない現状があります。暗い話ばかりしてしまいましたが、繰り返しになりますが、企業や社会とつながることで子どもたちの学びは増幅します。企業連携を推し進める方策も最後に考えてみましょう。
企業連携が進まない原因は、一言で言ってしまえば大人の認識にあります。
文科省の取り組みのように、行政が責任を持って仲介し、学校現場の負担を抑えながら子どもたちの力を育んでいくこと。その実践や子どもたちの姿を発信し、保護者をはじめ、社会の大人全体で子どもを見ていく重要性を啓蒙していくこと。受験制度や暗記偏重の学習を見直し、これから求められる新たな学びに改革していくこと。それを教育現場任せにするのではなく、こちらのメディアのような多くの媒体が発信してほしいと思っています。
学校現場の実態をより多くの大人が知り、批判するばかりでなく、共に考えられるような機会や場をつくっていくことが、これからの社会を担う子どもたちを支えていく、すべての大人の責務だと思うのです。
(注記のない写真:蓑手氏提供)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら