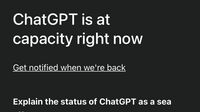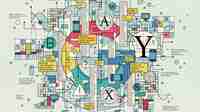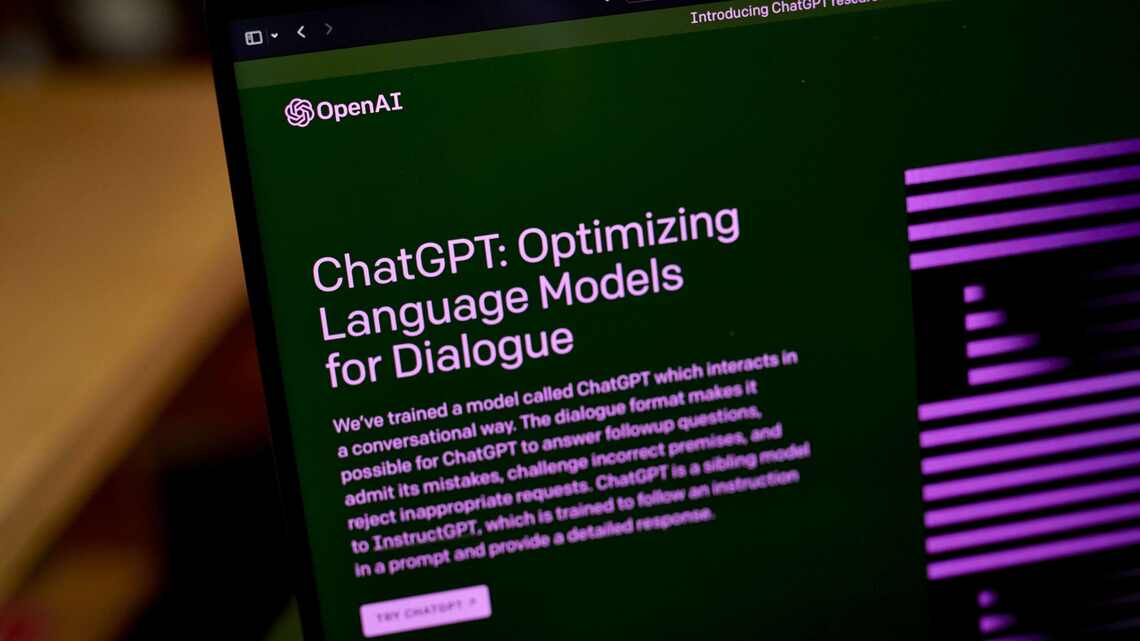
ノーザン・ミシガン大学の哲学教授、アントニー・オーマンが昨年12月、世界宗教のコースで提出された小論文を採点していたときのことだ。「このクラスで最も優れた小論文」の評点を余裕で獲得できる提出物に、オーマンは目を見張った。
ブルカ(イスラム教徒の女性が肌を隠すために全身を覆う衣服)を禁止する法律の道徳性を考察するその小論文は、適切な事例を盛り込んだ明快な文章で強力な議論を展開していた。
即座に赤信号が灯った。
オーマンが学生に、この小論文を本当に自分で書いたのかどうか問いただしたところ、学生は「ChatGPT(チャットGPT)」を使ったことを認めた。情報を処理し、概念を説明し、わかりやすい文章でアイデアを生成するチャットボットだ。
口頭試験や授業内小論文で「禁デジタル」
これに危機感を覚えたオーマンは、今学期から小論文の書き方を変えることにした。学生には第1段階の原稿を教室内で、コンピューターの使用を監視・制限するブラウザを使って書かせる予定だ。
以降の段階の原稿は、加えた修正について学生に説明を求める。次の学期からは、小論文の課題をなくすことも考えている。チャットボットGPTを授業に組み込んで、学生にチャットボットの応答を評価させることも計画している。
「これからの授業は『この問題について、私たち人間同士で議論しよう』といったものにはならない」。『私たちと違うロボットなら、この問題をどう考えるかについても議論しよう』といったものになるだろう」とオーマンは言う。