テクノロジー・アントレプレナーのオリバー・ラケットとジャーナリストのマイケル・ケーシーが述べているように、「コンテンツ消費者は劇の中で言えば、こちらに共感的な脇役にもなれば、完全な敵対者にもなる。どちらにしても、私たちと彼らとの相互作用が物語に肉づけをし、その印象を完成させる」からだ(『ソーシャルメディアの生態系』森内薫訳、東洋経済新報社)。ファンやオーディエンスにとって、アンチとの闘争は物語上の危機や山場として機能する。
とはいえ、コンテンツを供給する側も消費する側も、最終的にそれらをコントロールすることは不可能で、結果の予想も難しい。1つ言えることは、今後情報量がどれだけ増えたとしても、わたしたちの時間や神経活動には限界があり情報処理能力が進化することはないということだ。
「関心経済」がわたしたちを形作る
そうなると、ますますアテンション=関心の争奪戦は熾烈化し、巨大資本から個人までコンテンツ制作者は躍起になるだろう。「バズる」ことこそが至上の価値を持ちえるからだが、持ち上げるにしろ、叩くにしろ、特定のコンテンツに何がしかの反応を返すことは、ゴールドハーバーのいう「関心」、岡田のいう「評価」に与することである。
すでにわたしたちは、このようなダイナミズムが強力に作用するネットワークの中に生息しており、多かれ少なかれその価値基準が半ば無意識にまで浸透しつつある。
メディア論の泰斗であるマーシャル・マクルーハンは、いみじくも「私たちはツールを形作り、次にツールが私たちを形作る」と主張した。それにならえば、「関心経済」を形作ったのはわたしたちだが、今度は「関心経済」がわたしたちを形作ることになる。ネット上の「虚像」に神経を逆なでされ、自らも「虚像」の敵になるのは、そのごくごく一端の瑣末な現象に過ぎない。
「注目は金なり」が支配的になりつつある世界で、わたしたちは何に本当に関心を持つべきかを見極めねばならない。なぜなら、その浅くて早急な関心によって失われるのはほかならぬ自分自身の思考であるからだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

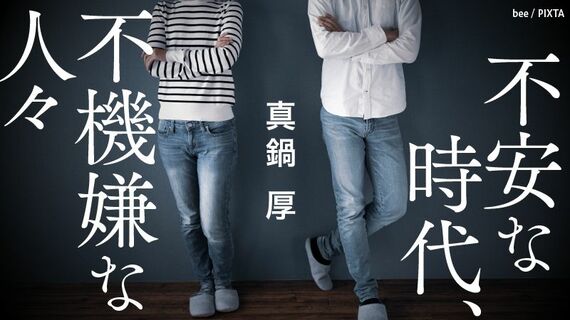






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら