「小規模校の探究学習」、人手不足・知識不足の課題にオンライン連携が解決策 カタリバ提供の「他校との交流」で生徒が輝く訳
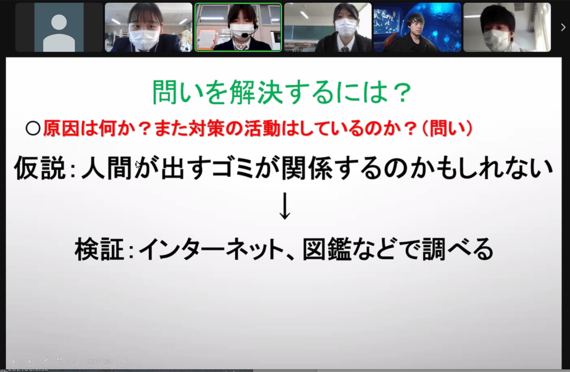
一方、別のグループでは、岩手県立大槌高校の男子生徒が「ウミガメ研究のお手伝い」をテーマに報告。こちらのグループは男子生徒同士だからか、互いの意見が重なり合い、笑いも巻き起こるなど対話は白熱。一方で、自分のテーマを語るときの真剣な表情も印象深かった。この後10分の振り返り、15分の感想共有を経て授業は終了した。

他校の生徒同士だからこそ生き生きと意見交換
複数の授業を見学したが、生徒たちは皆、緊張しつつも、前向きな姿勢で取り組んでいた。当初は、他校生同士で本当に授業が活気づくのかと疑問だったが、実際はむしろ他校の生徒に興味があるようで、やり取りも好奇心に満ちているように見えた。中には、サポーターのパスもあって他校の生徒に情報をもらったり、イラストやプログラミングのスキルで協同して何かできないか提案し合う場面も見られた。起塚さんが言う。
「1つの学校内では、自分のテーマに共感してくれる仲間がおらず、探究学習の入り口でモチベーションを失う子も出てしまいます。しかし、他校を探せば同じ興味を持った子はいる。そこで仲間を見つけることで探究への意欲も上がるのです。また、小規模校の生徒たちは子どもの頃から同じメンバーで過ごしていることが多いので、他校生との交流は何よりの刺激になるようです。他校生とは絶妙な距離感を保てますから、むしろ自分の殻を破ったり、本音を話したりするきっかけにもなるんですよ」
カタリバでは、授業から発展してさらにテーマや企画を深めたい、他校生と話したいという生徒に向けて、放課後に希望者が集う会合を行っている。ほかにも、教員向けにも探究学習に関する情報交換会を開催するなど、さまざまな連携活動に取り組んでいる。
今年から本格的に始まった「学校横断型探究プロジェクト」だが、今後はどのような展開を考えているのか。例えば、他校間との連携をさらに深めて、現状で年4回の授業をより日常的な活動にしつつ、将来的に100校ほどが集まれば、教育界に一定のインパクトを与えられるだろう。最後に、起塚さんは取り組みの意義についてこう語った。
「普段接することのない他校の同世代と交流することで、生徒は刺激を受けて意欲的に成長しているようです。他地域の生徒同士だからこそ、生き生きと語れることもある。このようにオンラインを活用すれば、距離の壁を越えられるだけではなく、これまでになかった新しいつながりを生み出すことができます。小規模校であっても、出会いの場、そして、学習の可能性を広げることは十分できますよ」
(文・國貞文隆、注記のない写真:ゲッティイメージズ)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























