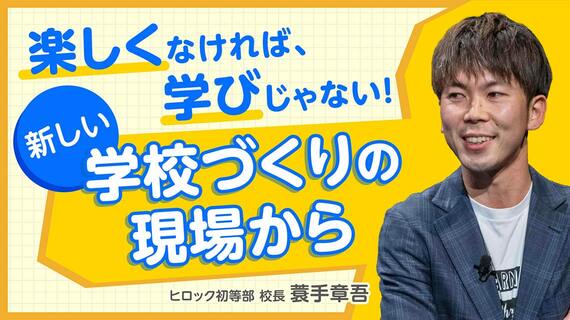さらに、こんなときだからこそ、ICT以前に学校の意義や教師の役割を確認し合うべきなんだと思います。ただ「ICTなんて面倒くさい」と考えているだけの教育関係者は論外ですが、子どもを取り巻く大人たちの大半は「子どもたちに幸せになってほしい」という点では一致しているはずなんですよね。みんなの思いを確認したうえで、現状の学校教育システムでは何が課題になっているのかを共通理解するのです。まずは課題の把握、次に解決のための方略を練る。そこで初めて、ICTが1つの選択肢として登場してくるのです。始めから「ICTありき」ではありません。
デジタルに慎重になる先生もいます。しかし多くの場合、その先生は子どものことを考えたうえでマイナスになると判断されているのです。理由やニーズをしっかり傾聴したうえで、ICTができることを「その先生が大切にしていること」をベースに理解してもらうことが重要です。
私は若い頃から、職場の先輩の影響もあり、これまでの日本の教科教育について学校外のセミナーなどでも学んできました。わが国が築き上げてきた教育のすばらしさもよく理解していますし、今でも役に立っています。だからこそ、デジタルに慎重になる先生方の気持ちも理解できるのです。そのうえで、私はICTを活用することが有効だと感じているので、これまでも率直にお伝えしてきたし、議論させてもらってきました。
今の若い先生方や専門家の方々、地域の方々も「あの先生は世間のことをまったくわかっていない」と一蹴するのではなく、これまでの教育が積み上げてきたものについて、もっと学ぶべきだと思います。そうしない限り、肯定派と否定派がお互い「相手は何もわかっていない」と言ってばかりで、本当に子どものためになるよい実践は生まれてこないのではないかと感じています。
ノウハウや研修は、ちょっと調べれば無料でいくつも手に入ります。専門家から教わらなくても、職場や保護者の方が普段使いされているような方法で、学び方は大きく変わります。私の経験から言えることは、お互いから学び合えるような時間を勤務時間内に設定すれば、確実に理解は進むということです。
先生方が心の底から「ICTが必要だ!」と思えれば、学校はいつからでも、いくらでも変われます。まずは、時間をかけてでも「共通了解」を探ること。対話を続けること。焦らず、土台を築いていきましょう。
(注記のない写真:EKAKI / PIXTA)
執筆:蓑手章吾
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら